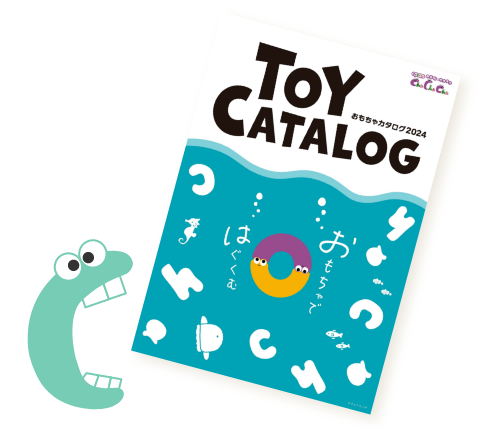おもちゃの正しい掃除・消毒方法とは?必要なものや作業工程を素材別で解説
おもちゃは子どもが直接触れるものなので、衛生面を気にする親御さんも多いのではないでしょうか。特に小さい頃は、おもちゃを口に入れたり、汚れたまま遊んだりするため、清潔に保つことが大切です。そこで今回は、おもちゃの正しい掃除・消毒方法や、作業工程を素材別でご紹介します。
おもちゃの基本的な掃除方法
おもちゃの掃除方法は、以下の3種類に大別されます。
- 水洗い
- 天日干し
- 除菌・消毒
まず覚えておきたいのは、おもちゃの素材により「適切な掃除方法は変わる」ということです。これには除菌スプレーなどの専用グッズを用いた除菌・消毒も含まれます。
掃除方法を誤ると、子どものお気に入りのおもちゃが痛んだり、傷ついたりする恐れがあります。おもちゃの素材や性質、形状なども考慮し、適切な方法でケアすることが大切です。それでは、各掃除方法のポイントを解説します。
目次
水洗い

もっとも基本となる掃除方法が水洗いです。子ども用おもちゃの多くは水洗いできるため、しっかりと乾燥させるだけで十分な洗浄効果が得られます。おもちゃの素材によっては、石鹸や洗濯用洗剤も使用可能です。ただし、木製おもちゃを筆頭に、水洗いや洗剤の使用を禁止している場合があるためご注意ください。おもちゃの説明書をよく読んで、水洗いできるかどうか確認しましょう。
UV除菌・温風除菌
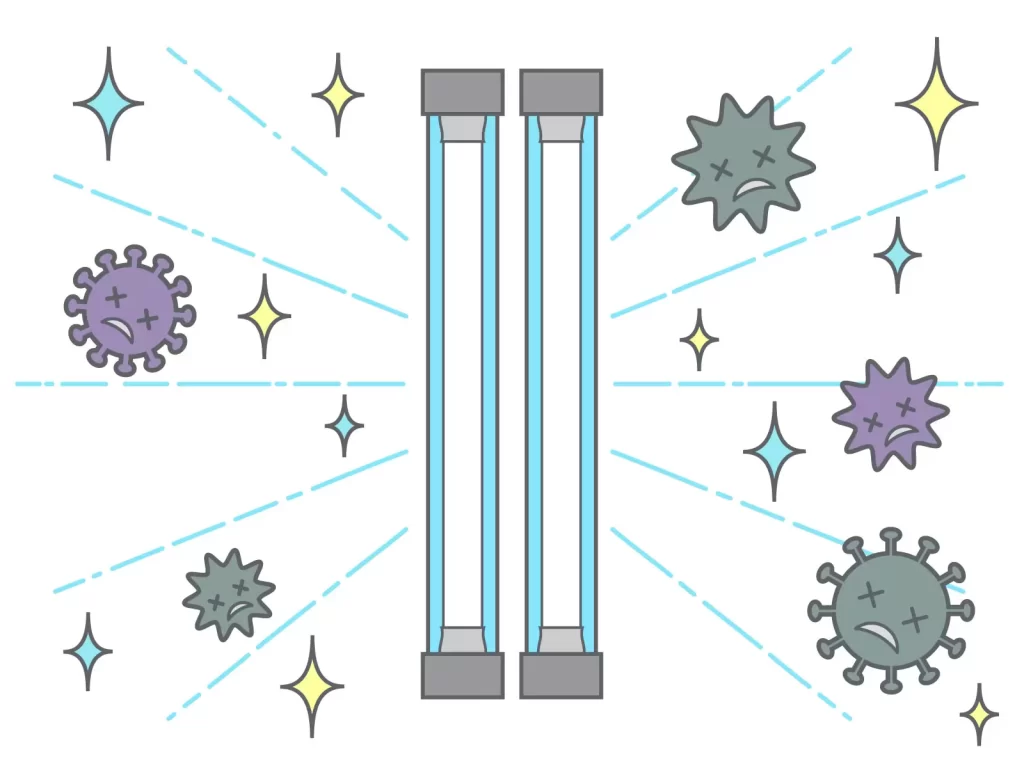
水洗いや洗濯が難しいぬいぐるみや木製のおもちゃなどは、UV除菌や温風機でケアできます。細かいゴミやほこりを飛ばせるほか、細かい菌においての殺菌も期待できるでしょう。
除菌・消毒

おもちゃ基本的に、水洗い・天日干しで十分綺麗になります。ただし、昨今は除菌・消毒に配慮している親御さんが少なくありません。
除菌・消毒をする場合、除菌シートやスプレー、酸素系漂白剤などを使いましょう。おもちゃの素材によっては、煮沸消毒も可能な場合があります。具体的な掃除方法や意識したいポイントは、以下の通りです。
除菌シートを使う
子どもや赤ちゃんの肌は繊細なため、使用する商品に含まれる成分によっては肌荒れを起こす可能性があります。したがって、除菌・消毒グッズは基本的にノンアルコールの商品を使用しましょう。おもちゃを頻繁に、口に入れる、すぐに噛んでしまう子の場合、ウェットシートを使ってください。精製水を用いたノンアルコールタイプのウェットシートは、肌への刺激が少ないので安心です。
除菌スプレーを使う
おもちゃの掃除に使う除菌スプレーは、ノンアルコールタイプかつアルカリ電解水の商品がおすすめです。原材料が塩と水であり、物や環境に優しいのがポイントです。ただし、子どもの肌に直接付着しないよう、取り扱いに注意してください。除菌スプレーのアルカリ成分が肌のタンパク質を溶かし、肌荒れする恐れがあります。
酸素系漂白剤を使う
酸素系漂白剤でおもちゃを漬け洗いします。手順としては、大きめのタライなどに酸素系漂白剤とおもちゃを投入し、2~3時間ほど漬けておきます。汚水を流した後、十分に水洗いして乾かしましょう。簡単なのに驚くほど汚れが落ちるので、複数のおもちゃをまとめて掃除したいときにおすすめです。
注意点として、海外製の酸素系漂白剤の使用は避けてください。洗浄効果が高い分、子どもや赤ちゃんの肌を傷つける恐れがあります。「ベビー用酸素系漂白剤」や、天然素材を使った日本製の酸素系漂白剤を使いましょう。
煮沸消毒する
「歯固め」など口に入れるもの、プラスティック製のおもちゃ全般は煮沸消毒がおすすめです。哺乳瓶も使用している場合は、一緒に煮沸消毒すると効率的です。煮沸せずとも、熱湯に15~20分程度漬けるだけでも消毒できます。
おもちゃの消毒に関する基礎知識
「おもちゃは小まめに消毒するもの」と考える親御さんは少なくありません。雑菌が小さな子どもに害をなす可能性があるのは事実です。しかし、神経質に消毒するのもまた、望ましくないとされます。ここでは、消毒の定義とは何なのか、どういったタイミングで行うのが理想なのかお話します。
消毒とは?
一般に消毒とは、雑菌を無力化し、毒性や感染力を失わせることの総称です。「薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)」にもとづき、医薬品または医薬部外品において表示が許されます。
消毒の関連用語として、抗菌や除菌、殺菌や滅菌(めっきん)が挙げられます。それぞれ違いは次の通りです。
- 抗菌:雑菌の増殖を抑制すること
- 除菌:対象から雑菌を取り除くこと
- 殺菌:雑菌を殺して無害化すること
- 滅菌:有毒性にかかわらず、すべての菌を除去すること
「殺菌消毒」という言葉があるように、消毒と殺菌は同様の意味を持ちます。ただ、薬機法においては扱いが別物です。「病原性微生物を無力化する度合い」としては、比較的強い部類に入るでしょう。
そんな消毒ですが、おもちゃにおいては定期的な実施が「望ましい」とされます。とりわけ未満児は抵抗力が低く、雑菌が付着したおもちゃを口に入れることも少なくありません。定期的に掃除・消毒し、衛生状態を維持したいところです。
一方、雑菌には子どもや赤ちゃんの免疫力を高める働きがあります。親が神経質になって消毒ばかりすると、ウイルスや病原菌から身体を守る免疫力がつきにくくなるでしょう。結果、風邪を引きやすかったり、病気になりやすかったりする可能性があります。おもちゃの消毒は大切ですが、逐一行うものではないこと覚えておきましょう。
適切な消毒のタイミングとは?
おもちゃの消毒に対し、神経質になる必要はありません。しかし、以下の場合はできるだけ消毒することをおすすめします。
- ほかの子どもと遊んだとき
- ほかの子どもが使ったおもちゃに触れたとき
- 外出したとき
- 本人または兄弟が風邪を引いているとき
前提として、おもちゃの消毒タイミングや頻度に
雑菌は外から持ち込まれるものです。おもちゃを外に持ち出したり、ママ・パパ友や親戚の子どもが遊びにきたりした際は、消毒を徹底しましょう。特に注意なのは、ほかの子どもが使ったおもちゃに触れたときです。その子を起因として、ウイルスなどに感染する恐れがあります。手はもちろんのこと、使用後のおもちゃもしっかりと消毒しましょう。
本人や兄弟が風邪を引いているときも注意が必要です。ウイルスがおもちゃに付着するため、できる限り消毒してください。いずれにしても、感染リスクが生じる場面では、積極的におもちゃを消毒しましょう。
【素材別】おもちゃの正しい掃除方法・消毒テクニック
ここでは、おもちゃの正しい掃除方法や消毒テクニックを素材別でご紹介します。木製・プラスティック製・布製の3種類に加え、お風呂で遊ぶおもちゃの掃除方法にも触れますので、ぜひ参考にしてください。
木製のおもちゃ

木製のおもちゃは原則、水や洗剤で丸洗いできません。天日干しが基本となりますが、天気模様によっては難しいでしょう。室内で行えるケアとしては、固く絞った濡れふきん、またはノンアルコール除菌シートで数回拭くのがおすすめです。3回を目安に拭くことで、一定の洗浄効果を確保できます。
ここで重要なのは、「陰干し」をすることです。木材は水分に弱く、しっかりと乾燥させないと歪んだり、表面に水ジミができたりします。消毒後は必ず陰干しを行い、水気を取りましょう。
このほか、「次亜塩素酸水」を用いる方法があります。漂白剤で知られる次亜塩素酸水ですが、その消毒製と安全性の高さから、おもちゃの消毒に使用されます。後述する「おもちゃのサブスク(サブスクリプションサービス)」においても、次亜塩素酸を主成分とした「プロトクリン」と呼ばれる除菌消臭水が使われています。子どもの身体に優しく、確かな洗浄力および消毒効果が得られるものです。
プラスティック製のおもちゃ

アルカリ電解水の除菌スプレーを拭きかけ、コットン製のクリーニングクロスで磨きます。ノンアルコール除菌シートで拭いても、水洗いと乾燥で済ませても問題ありません。除菌・消毒を重視する場合は、スプレーまたはシートなどの専用グッズを使用してください。
補足ですが、おもちゃの掃除に消毒用アルコールを用いて問題ありません。ノンアルコールタイプが子どもの肌やおもちゃ本体、環境に優しいのは確かです。しかし、消毒や殺菌を重視するならば、度数77~78%の消毒用アルコールを使うのも、ひとつの選択といえるでしょう。
アルコールは短時間で蒸発する揮発性の高い液体です。そのため、消毒用アルコールを用いても、おもちゃの表面に残留する可能性は低く、肌荒れなどが生じるリスクは低いと考えられています。実際に、知育玩具を扱う業界においても、消毒用アルコールによる洗浄が行われています。
ただし、強い「アルコールアレルギー」を持つ子どもの場合、わずかに残留したアルコール成分に反応し、肌荒れを起こすリスクは否めません。アルコールアレルギーの度合いについては、予防接種時に行う消毒において判断がつきます。個人で消毒用アルコールを使用する場合、かかりつけ医に確認を取ると安心です。
このように、プラスティック製のおもちゃについては、ノンアルコールの除菌シートや除菌スプレーを使うのが基本です。より消毒効果を望む場合、消毒用アルコールの使用を検討してください。
布製のおもちゃ

布製おもちゃは、基本的に洗濯機などで丸洗いすることができます。ただし、洗濯NG表記のあるもの、説明書にお手入れの方法が記載されていないもの、フェルト素材のものは洗濯機で洗うことはできません。
洗濯機を使用する場合、洗濯ネットに入れてから洗います。これはおもちゃの付属品が流されるのを防ぐためです。また、型崩れが気になる布絵本などは、手洗いがおすすめです。洗剤がおもちゃに残らないよう、乾いたタオルで押すように水気を取りましょう。天日干しまたは乾燥機にかける前に、しっかりと脱水するのがコツです。
フェルト素材については、洗濯できるもの・できないものがあります。おもちゃの説明書や商品パッケージに記載されているため、洗濯の可否を確認しましょう。無理に洗濯をした場合、毛玉や毛羽立ちの原因となります。
基本的なお手入れ方法としては、濡れふきんで表面を軽く叩きます。水気を帯びたら風通しのいい場所で陰干ししましょう。毛羽立ちが気になったら、アイロンでなでるように押さえます。
お風呂で遊ぶおもちゃ

例外的に、お風呂で遊ぶおもちゃは小まめな除菌・消毒をおすすめします。プラスティック製の商品が多く、放置すると皮脂汚れや水垢汚れ、黒カビの繁殖を招きます。重曹や酸素系漂白剤を使い、定期的に洗浄しましょう。
もっとも手軽なのは、重曹と歯ブラシを使った洗浄です。おもちゃを水で濡らした後、まんべんなく重曹を振りかけます。続いて歯ブラシで細部まで磨き、冷水ですすいでください。重曹が残留しないよう、しっかりとすすぐことが大切です。
注意点として、磨く際に力を入れ過ぎるとプリントなどが剥がれる恐れがあります。力加減に気を配りつつ、隅々まで磨くのがコツです。すすいだ後は、乾いたタオルで水気を取りましょう
消毒済みのおもちゃが届くサブスクサービスとは?
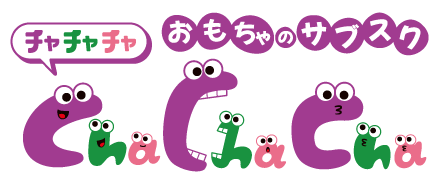
おもちゃのサブスクとは、おもちゃ・知育玩具の定額レンタルサービスのことです。代表的なサービスに「ChaChaCha」が挙げられます。
「ChaChaCha」では4つの料金プランを用意しています。メインとなる「基本プラン」は、定価15,000円以上のおもちゃが隔月で届く0~6歳向けのプラン。1日あたり110円で、さまざまな知育玩具をレンタルできるのが魅力です。
実際に届くおもちゃは、子どもの月齢・年齢や、契約時のヒアリング内容にもとづいて保育士などのプロが選定したものです。もちろん、発送する知育玩具の衛生管理は徹底されています。
お客様からご返却いただいた知育玩具は、検品後に清掃・消毒を行います。たとえば、プラスティック製のおもちゃは、高温スチームによる熱処理と消毒清拭を行った後、乾燥後はポリ袋に密閉します。77度以上の消毒用アルコールを使いますが、徹底的に乾燥させることで、アルコールの残留を防止し、身体への影響をなくしているのが特徴です。このように、プロの手で掃除・消毒された品が届くのも、おもちゃのサブスクの魅力といえます。
まとめ
おもちゃの掃除・消毒は、神経質になり過ぎないことが大切です。雑菌が触れるのは好ましくないですが、頻繁に消毒しすぎると子どもや赤ちゃんの免疫力を弱めてしまう場合もあります。よほど汚れていたり、状態が悪かったりしない限り、そのまま遊ばせて問題ないでしょう。
「掃除が手間……」と感じるなら、隔月で新しいおもちゃが届くサブスクを利用するのがおすすめです。「ChaChaCha」を筆頭に、おもちゃの衛生管理を徹底しているサービスは多数あります。まずは料金プランとサービス内容の確認から始めましょう。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!