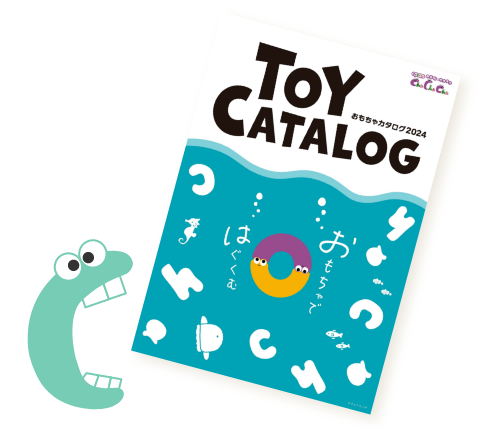新生児のおもちゃはいつから必要?選び方やおすすめのおもちゃを紹介
まだ1人で遊ぶことのできない新生児の玩具選びには、悩みがつきもの。「必要ないのでは?」「早すぎない?」と考えるママ・パパも少なくありません。そこで今回は、新生児の赤ちゃんにおもちゃが必要な理由をはじめ、最適な知育玩具の選び方をご紹介します。
新生児におもちゃは必要?その理由は?
まずは、新生児の赤ちゃんにおもちゃが必要な理由や、発達・発育の影響を解説します。1人では遊べない赤ちゃんになぜ、知育玩具が必要とされるのでしょうか?
五感を刺激する
新生児の時期は、目や耳がまだ未発達です。しかしながら、その時期に玩具に触れされることで、五感の発達を促します。
生後一年間は、脳が著しく成長・発達するといわれています。そんな赤ちゃんに対しておもちゃは、さまざまな「体験」を与えるのです。具体的には、赤ちゃんの好奇心を利用して身体能力や色彩感覚、想像力など、さまざまな能力を引き出すお手伝いをします。
親子のコミュニケーションになる
新生児は、おもちゃを握ることもまだ難しく、一人では遊べません。そのため、ママやパパが揺らしたおもちゃを見つめたり、音を聴いたりして、能動的な刺激を受けます。
また、言葉をかけながらおもちゃで遊ぶことは、親子のコミュニケーションになります。昨日まではできなかったことができるようになる我が子の成長を間近で見られるでしょう。なお、赤ちゃんが玩具を使って一人で遊べるようになるのは、個人差がありますが生後2〜4ヶ月頃が多いです。
新生児向けのおもちゃの選び方とは?
視覚や聴覚がまだ発達していない赤ちゃんは、口に入れることで形や匂いなどを確認します。自分の手を認識した生後2ヶ月以降に多いですが、新生児時期には誤飲リスクもあります。玩具を選ぶ際には、以下のことを考慮して選びましょう。
安全性が高いか
身体に害のある塗料が使われていないか、口を傷つける鋭利なパーツはないか、誤飲の恐れがあるサイズではないかなどを、さまざまな観点からおもちゃの安全性を確認しましょう。小さな手でも握りやすく、落としても壊れない丈夫なおもちゃが最適です。
安全なおもちゃを選ぶのが難しい場合、玩具の安全基準に合格した「STマーク」つきの製品を選びましょう。また、玩具には対象年齢が設けられています。事故を防ぐためにも、対象年齢に合った製品で遊ばせてください。
衛生面やメンテナンス性は十分か
玩具に手汗やよだれがつくことも考慮し、お手入れのしやすい製品を選ぶようにしましょう。アルコールシートでさっと拭き取れるもの、手洗いできるものがおすすめです。マットが付いたジムなどのおもちゃは、分解して手洗い・洗濯洗いができるか確認してください。個別に洗浄できるおもちゃは衛生的で、新生児の赤ちゃんにも最適です。
感覚発達を促すおもちゃか
新生児の赤ちゃんには、優しい音のなる玩具やぬいぐるみのような柔らかい肌触りのおもちゃがぴったりです。五感が未発達の赤ちゃんにとって、視覚・聴覚などの刺激が強すぎる玩具は避けてください。また、この時期の赤ちゃんは成長が早いため、月齢に合わせて異なる遊び方ができるおもちゃを選ぶといいでしょう。
新生児におすすめのおもちゃ10選
ベビーズFUNFUNジム
さまざまな指遊びが楽しめるジムです。にぎったりひっぱったりすることで音がなるしかけが赤ちゃんを楽しませます。ねんね期には、ママやパパが仕掛けを揺らすことで、追視やリーチングを促したり、足元のプロペラをキックしたりして、全身運動につながります。
お座りができるようになったら、目線の高さにある仕掛けでひとり遊びもできるでしょう。つかまり立ちの時期にはジムを支えとして使用できます。成長に合わせて長い期間使用することができるのが魅力。手洗いやアルコール消毒が行えるため、お手入れも楽々なおもちゃです。
やわらかふわふわメリー
ハチやくまさん、てんとう虫など赤ちゃんにとって馴染みのあるぬいぐるみがやさしいメロディに合わせて回るメリーです。付属のスタンドや背面ベルトでフロア以外にベビーベッドに取り付けて使用することができます。
収録されている音楽は、キラキラ星やゆりかごの歌など、心を落ち着かせてくれるものばかり。優しい音楽と水のせせらぎや鳥のさえずりといった自然音も収録されています。ねんね期には、顔の上でゆっくりと回るぬいぐるみが赤ちゃんの興味を引きます。ぬいぐるみは取り外しが可能で、ラトルとしても遊ぶことができます。
指遊びミュージカルジム
カラフルな動物が描かれたマットが付いたジムです。取り外し可能なアーチには、さまざまな仕掛けが施された動物を取り付けることができます。ねんね期には、手を伸ばして動物に触れようとすることでリーチングを促します。
腹這い期には、おもちゃをアーチから外してマットにおくことで腹這いのきっかけづくりにも。また、お座り期には、キリンさんのラトルやカチカチ音の楽しいクラッカーなどで、手指を動かして遊べます。さまざまな種類のおもちゃを通じて、遊び方や音の出し方を学び、思考力を鍛えられるおもちゃです。
ぐ〜ぐ〜ひつじのシアター
ひつじのイラストが投影されるシアターです。お子様の情緒をサポートする優しいメロディが眠りに誘います。声を感知するとメロディが流れるサウンドセンサーがついているため、泣き止ませるためのきっかけにも最適です。
月の部分はライトになっており、授乳やおむつ替えに便利です。背面にベルトがついているため、床に置く以外にベビーベッドへの取り付けも可能。眠る前のルーティーンにすることで、眠る習慣づくりにも最適です。
タミータイム・プロップ&プレイ
しろくまのデザインがかわいいプレイマットです。ねんね期から使用することができ、さまざまな場所に施されたカラフルなタグがお子様の興味を引きます。おもちゃに手を伸ばすことで全身運動にもなるでしょう。
腹這い期には、手についたソフトミラーで顔を映し自己認識を促す効果も期待できます。手触りが異なる素材が使用されているため、触感の違いを感じられます。手洗いが可能なため、日常的なお手入れも簡単です。
スターブライトシンフォニー
ほっぺたが光るお星様のメロディトイです。カラフルな色合いで、赤ちゃんにも認識しやすく興味を持ちやすいです。周りはナイロンでできている、赤ちゃんの好きなシャカシャカ素材。触って音を楽しんだり、舐めたりカミカミして感触を確かめます。
星の部分を叩いたり揺らしたりすると音楽が鳴り、動きと音の因果関係を学ぶ効果も。連続再生モードがあるので、音を鳴らし続けることができます。ベビーカーに取り付けられるためお出かけにも便利なおもちゃです。
ベビープレイネスト
日本ではまだあまり馴染みのないプレイネストは、海外では定番かつ大人気のおもちゃです。遊び方はシンプルで、浮き輪型になったクッションに赤ちゃんをお座りさせておくだけ。料理中など、別の作業をしながら赤ちゃんを見守りたいときに役立ちます。
空気の量を調節することで、ねんね期の赤ちゃんでも遊べます。お座りができるようになれば、空気を増やし後ろに倒れた際の事故を防止。クッションには、あそびのしかけがたくさんついていることで、遊びの空間としても機能します。
ベビープレイマットトロピカル
マットに描かれたライオンやゾウのイラストが可愛らしいおもちゃです。ねんね期には、葉っぱ型のラトルをママやパパが振ってあげることで、揺れる動きと音が五感を刺激します。
ピローは、赤ちゃんが認識しやすいモノクロ柄を採用しました。また、鏡のおもちゃで赤ちゃんの顔を映してあげることで自己認識を促します。マットは洗濯可能で簡単にお手入れできるのが嬉しいです。
全身を刺激セルフメリー
20年のロングセラーを誇るセルフメリーです。カシャカシャ音が楽しいブランケット部分からは大きなキリンさんが顔を覗かせます。体にかけると足でケリケリして布の感触を感じながら、自分の足の認識をサポートします。
揺らすとリンリンといった音がするリンゴで、親子で一緒に遊びましょう。バウンサーやベビーカーにも取り付けが可能なため、料理中や移動時の玩具としても役立ちます。
ぐるぐるタグブランケット
ふわふわな手触りが新生児の赤ちゃんにも優しいブランケットです。カラフルなタグを触ってみたり、鈴の音のなるおさかなのマスコットで指先や目、耳を刺激します。
ブランケットとして使うことで、柔らかい布の感触を体で感じることも。ベビーカーに取り付けられるリング付きで移動中の落下を防ぎます。小さく場所も取らないため、お出かけにも便利です。
新生児の知育玩具は「ChaChaCha」でレンタルしよう
お子様の成長に合わせ、その都度新しい知育玩具を購入するのは、あまり得策とはいえません。金銭的にも負担は無視できませんし、何より月齢に合わなくなったおもちゃの収納に手を焼きます。そこでおすすめなのが、必要な時期に、必要な知育玩具を借りられるおもちゃのサブスクです。
「ChaChaCha」では、400種類を超える有名ブランド知育玩具の中から、お子様一人ひとりにぴったりのおもちゃを選定してお届けします。月齢・年齢はもちろん、事前に記入いただくヒアリングシートの内容を考慮し、現役保育士など幼児教育のプロが自信を持って最適なおもちゃを厳選します。
また、レンタルしたい知育玩具のメーカーや、製品を個別に指定できます。これについては「ChaChaCha」の公式サイトにある「カタログ」からお選びください。料金やサービス内容、おもちゃごとに得られる知育効果も含め、気になることは公式サイトの各ページをご覧ください。
まとめ
今回は、新生児におもちゃが必要な理由について紹介しました。新生児だけでなく、年齢・月齢に適した知育玩具で遊ぶことは、お子様の成長・発達に好影響をもたらします。「本当に必要?」と悩む前に、まずは親子で一緒に遊んでみましょう。知育玩具の用意で困ったときは、ぜひおもちゃのサブスクである「ChaChaCha」をご利用ください。
新たに訴求見出しを作成しました。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!