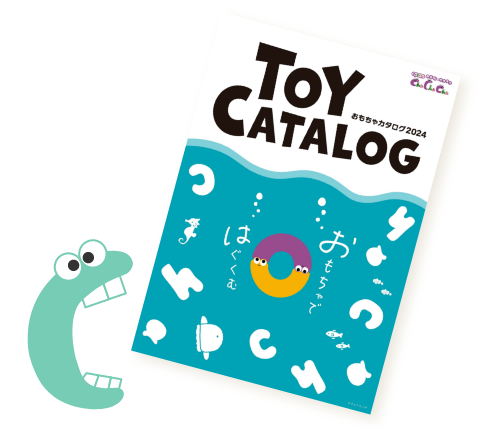「イヤイヤ期」はなぜ起こる?対処法や心理について解説
子育てをする上で、「イヤイヤ期」は避けて通れない期間です。イヤイヤ期は2歳前後から始まり、「イヤ!」「ダメ!」という言葉を多用する特徴があります。その大きな変わりようから「魔の2歳児」と呼ばれ、ママ・パパを悩ませる大きな要因です。そこで今回は、イヤイヤ期の理由や対策、子どもの心理状況をご紹介します。
目次
イヤイヤ期とは?
一般的にイヤイヤ期は2歳前後から始まり、日常のいろいろな場面で拒否・反抗を示す期間のことです。まずは、イヤイヤ期の基礎知識をおさらいしましょう。
イヤイヤ期の特徴
イヤイヤ期とは、子どもの自己主張が強くなり、自分の気持ちを押し通そうとする時期の総称です。「第一次反抗期」ともいい、一般的に2歳前後から3歳頃まで続きます。
この時期は、子どもの自我・自立心が発達し始めるため、さまざまなことを1人でやりたがります。そのため、大人の助けを嫌がる場合も少なくありません。親にとっては大変な時期ですが、落ち着いてポジティブに対応することが大切です。
イヤイヤ期では、「ワガママになった」「なぜいうことを聞かないの?」と悩むかもしれませんが、我が子が人として成長する大切な機会と捉えましょう。
イヤイヤ期は何歳から始まる?
イヤイヤ期のピークは2歳過ぎで、1歳半ごろから思い通りにならないときに「かんしゃく(癇癪)」を起こす子が多いようです。イヤイヤ期は3~4歳で落ち着くことが多いですが、実際は個人差があります。
この時期をスムーズに乗り切るため、ママ・パパはが子どものイヤイヤ期に振り回されず、ストレスを溜めないことが重要です。もし子どものイヤイヤ期に悩んだ場合は、身近な人や専門家に相談するといいでしょう。
イヤイヤ期の理由と子どもの心理
イヤイヤ期は、自立心が芽生え、自分の意思を主張し始める精神的発達の段階で起こります。子どもは、親の意見ではなく「自分のやりたいようにしたい」という意識が強くなります。
イヤイヤ期が起こる原因は、脳の「前頭前野」の発達が不十分なことに起因します。前頭前野は、大脳の前方に位置し、人が人らしくあるために欠かせない機能を持つ部位です。
具体的には、「思考する」「記憶する」「物事を決める」「我慢する」や「感情を制御する」などの役割があります。幼児はこの部分の発達が未熟なため、自分の意思を主張したり、感情を爆発させたりすることが多くなるのです。
子どもが自分や他者の気持ちを理解し、感情を伝えたり抑えたりできるようになれば、次第にイヤイヤ期は落ち着きます。何より、この時期に自己主張をする経験が欠如すると、思春期にトラブルで苦しむ可能性があります。
この時期にしっかり自己主張ができないと、自分の意志が弱くなったり、周囲と主体的に関わろうとする気持ちを持てなかったりするという説もあります。また、意見の異なる相手とのコミュニケーションがうまくいかないなど、社会生活に支障をきたす可能性があります。
イヤイヤ期の子どもは、その心理を正しく理解することが大切です。叱って押さえつけるのではなく、親として上手な対処を身につけ、スムーズに乗り切りましょう。
イヤイヤ期を乗り越えるための対策とポイント
イヤイヤ期の対応策として、子どもを「1人の人間」として尊重し、接することが大切です。イヤイヤ期を乗り越えて精神発達を促すためにも、周囲の大人は正しい接し方を心がけましょう。
ここでは、イヤイヤを乗り越えるための対策とポイントを解説します。
子どもに理解を示す
まずは、子どもの自己主張や感情を受け入れることが大切です。
この時期で重要なのは、子どもへの接し方です。たとえば、子ども服を買う際に「赤い服と青い服、どっちがいい?」と聞いてみましょう。子どもに選ばせることで、物事を自分の意思で決める練習になります。そして、イヤイヤ期特有の「自分のやりたいようにしたい」気持ちを満たせるのです。
また、子どもがいうことを聞かなかったり、意見に反発したりしても、気持ちを一度受け止めると、安心して気持ちを切り替えやすくなります。
反対に「いうことを聞いて」「ダメといったらダメ」など、強く否定するのはNGです。イヤイヤ期の子どもが「そもそもなぜダメなのか?」「どうして自分の主張を認めないのか?」を理解するのは難しいでしょう。
子どもの健やかな成長のためにも、まずは、子どもに理解を示し、受け入れる姿勢が大切です。
子どものストレスケアを心がける
イヤイヤ期は子ども自身にもストレスのかかる時期です。ストレスケアのため、「イヤイヤの原因に対処する」「スキンシップをはかる」などの対処も必要でしょう。
親は子どもとのコミュニケーション頻度を上げ、子どものやりたいこと、苦手なこと、伝えたいことをできるだけくみ取りましょう。
親のストレスケアも大切
なお、イヤイヤ期では親側のストレスケアも欠かせません。「誰もが振り回される時期」と割り切った上で、ストレスを抱え込まないよう意識します。たとえ感情的になったり大声を上げたりしても、あまり落ち込まないようにしましょう。怒りすぎたと感じたら、素直に「ごめんね」と伝えればOKです。
ストレスを感じたら、周囲に助けを求めてください。同年代の子を持つ親と話したり、パートナーに家事を任せたりしてもいいでしょう。
また、「イヤイヤされても大丈夫な場所に行く」「一人の時間を作る」「自分へのご褒美を用意する」といったストレス解消法もあります。イヤイヤ期で親と子、双方がストレスを抱えるのは悪循環です。子どもだけでなく、親側にも適度な「ガス抜き」が欠かせません。
専門家のサポートの受ける
イヤイヤ期の長さや拒絶反応には個人差があり、子ども一人ひとりに適した対応や、細かいケアが欠かせません。一方、「我が子にはどう接したらいいのだろう?」と悩むママ・パパが多いのも事実です。その場合、子育てや幼児教育の専門家に相談するといいでしょう。
以下、専門家のサポートが受けられる施設・サービスの一例です。
- 子育て支援センター
- 地域保健センター
- 児童相談所
- 子育てホットライン
- オンラインカウンセリングサービス
もっとも身近なのは、地域の子育て支援センターです。ここでは、保健師をはじめとする専門スタッフに子育ての悩みを相談できます。たとえば、イヤイヤ期の子どもの様子を聞いてもらった上で、最適な接し方や振る舞いに関するアドバイスを受けられます。
また、子育て支援センターでは「子育て教室」や「育児講座」を開催しています。イヤイヤ期との向き合い方など、具体的な情報が得られるので、興味のある人は参加してみましょう。
専門家のサポートは、電話やメール、ビデオ通話でも受けられます。たとえば、子育てホットラインで有名な支援サービスに「ママさん110番」があります。これは「日本保育協会」が提供する電話相談サービスで、保険員や相談員が育児などの悩みを聞き、アドバイスをしています。
近年は、Web会議ツール「Zoom」を使ったオンラインカウンセリングサービスが登場しました。これは「コロナ禍」で一気に普及したサービスで、カウンセラーとビデオ通話でやりとりします。相手の表情や雰囲気がわかりやすく、質の高いサポートを受けられると人気です
イヤイヤ期とおもちゃの関わりとは?
イヤイヤ期の子どもには、知育玩具をはじめとするおもちゃでたくさん遊ばせるとよいでしょう。上記の通り、この時期は子どもの自我が形成される大切な時期です。興味関心の幅が広がり、「何かに挑戦したい」という欲求も高まります。
知育玩具で遊ぶことで、子どもは自分の意志や感情を表現できます。その中でストレスを緩和させたり、自己肯定感を高めたりすることもできるでしょう。
また、おもちゃは子どもに選ばせるのがポイントです。イヤイヤ期では親の意見を拒否するケースが多く、親が選んだおもちゃを買っても遊ばないかもしれません。自分が選んだおもちゃで、満足いくまで遊ばせることが重要です。
知育玩具はレンタルがおすすめ?
現代の幼児教育では、さまざまな、知育玩具が活用されています。幼稚園・保育園はもちろん、家庭内でも知育玩具を使った遊びが定着しています。
知育玩具には対象年齢が設定されており、成長とともに買い足すのが一般的です。しかし、新品の知育玩具は割高なものが多く、「お財布が……」と悩むママ・パパも多いでしょう。そこでおすすめしたいのが、知育玩具の定期レンタルサービスである「おもちゃのサブスク」です。
おもちゃのサブスクは、お子様の成長や発達を促すおもちゃが手元に届く便利なサービスです。基本は月額制で、毎月・隔月のスパンで新しいおもちゃが送られてきます。高価なおもちゃも安く借りられるため、コストパフォーマンス抜群のサービスです。
おもちゃのサブスクのメリットは、コスト面だけではありません。たとえば、おもちゃのサブスクを利用することで、自宅のスペースを節約できます。
基本的にレンタルしたおもちゃは、一定期間ごとに交換となります。定期的に返却するため、自宅がおもちゃだらけになるのを防ぐことができます。必要なときに、必要な数のおもちゃを用意できるのが、サブスクの魅力です。
おすすめのサービスは「ChaChaCha」
おすすめのおもちゃのサブスクは、初月1円から始められる「ChaChaCha」です。「ChaChaCha」では、現役保育士をはじめとする幼児教育のプロがおもちゃを選定します。あらかじめお子様の成長の様子をヒアリングし、最適なおもちゃをお届けするサービスです。
「ChaChaCha」はイヤイヤ期のお子様のいるご家庭にもぴったりのサービスです。一度に5〜6点のおもちゃが届くため、日常の遊びで困ることがありません。また、定期的に新しいおもちゃと交換するので、常に新鮮な気持ちで遊べます。「次はどんなおもちゃが届くのかな?」「これはどんなおもちゃだろう?」とワクワクできるでしょう。
「ChaChaCha」では複数の料金プランを用意しています。通常利用であれば、月額3,630円(税込)の基本プランがおすすめです。1日あたり117円で、総額15,000円相当のおもちゃをレンタルできます。気になる方は、一度公式サイトの料金プランやサービス内容をご確認ください。
まとめ
イヤイヤ期は子どもと親、どちらにとっても試練の期間です。本記事を参考に、イヤイヤ期の原因や対策、スムーズに乗り越えるためのポイントを押さえましょう。
合わせて、知育玩具を積極的に活用してください。遊びは子どものストレス解消であり、成長と発達に欠かせないものです。おもちゃのサブスクを上手く使えば、毎日の遊びがより楽しくなるでしょう。
この記事の監修者

五十嵐 麻弥子
フリーライター/上級心理カウンセラー/不登校支援カウンセラー。
出版社勤務を経てフリー編集ライターに。子育て・教育・医療・健康を中心に、さまざまな媒体で執筆多数。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!