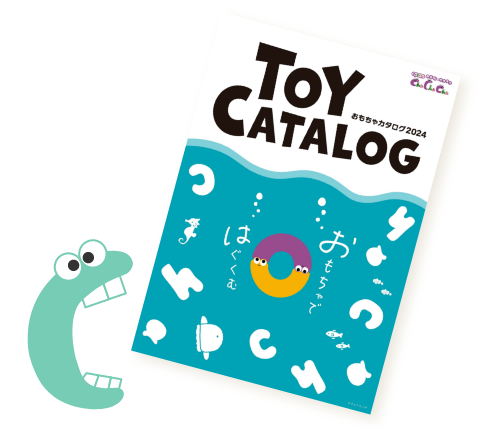モンテッソーリ教育とは|特徴やメリット、おすすめの知育玩具をわかりやすく解説
子どもにとって「よりよい教育を」と考えるママ・パパも少なくありません。世界中にはさまざまな教育法があり、日常的な子どもとの関わり方や、保育園・幼稚園選びに迷っている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、将棋界で躍進を続ける「藤井聡太」名人が幼少期に取り入れていたことで話題となった教育法があります。それが「モンテッソーリ教育」です。古くから世界各国で実践されている教育法で、日本でも取り入れている保育園・幼稚園があります。そこで今回は、モンテッソーリ教育の特徴やそのメリット、おすすめの知育玩具についても紹介します。
目次
モンテッソーリ教育の基礎知識
現在では、世界140カ国以上で導入されているモンテッソーリ教育。著名人を多く輩出した教育法としても知られています。まずは、モンテッソーリ教育の基礎知識についてご紹介します。
モンテッソーリ教育とは?
モンテッソーリ教育とはいわば、子ども主体の教育法です。日本で一般的となっている「教師が一方的に知識を与える教育法」とは異なり、子どもの自発性を尊重し、自分で課題に取り込むことで結果を導き出すプロセスを重視しています。
モンテッソーリ教育の基本的な考え方には、「自己教育力」があります。それは、子どもが持つ「自立・発達していこうとする力」です。自己教育力を発揮するためには、大人が発達の進み方を知り、子どもに見合った環境を整える必要があります。
乳幼児期は「敏感期」とも呼ばれ、何かに強く興味を持つ期間とされています。この時期の子どもは、集中して同じことを繰り返すものです。たとえば、物の出し入れを何度も行ったりするのがこれにあたります。
モンテッソーリ教育では「教具」と呼ばれるものを使用し、子どもの好奇心を刺激します。知育玩具に近いものであり、一部は代用可能です。また、暮らしや環境の中にある物の使い方をわかりやすく伝えることも、モンテッソーリ教育において重要なプロセスです。いずれにしても、子どもに「やってみたい」という気持ちを芽生えさせることが、大人の役目といえるでしょう。
モンテッソーリ教育の歴史
20世紀初頭のイタリアで考案されたモンテッソーリ教育は、マリア・モンテッソーリによって提唱された教育法です。イタリア人女性初の医学博士であったマリア・モンテッソーリはその当時、精神病院で医師として働いていました。
1907年、彼女は障害児教育に携わる中で、知的障害のある子どもの治療教育を目指した「こどもの家」を設立。そこで行われた教育法が注目を浴び「モンテッソーリ教育」と呼ばれました。
この教育法は、欧米諸外国を中心に広がります。アメリカで二度、モンテッソーリブームが起こり、同国では主流の幼児教育法となりました。また、日本でも1960年代に広まり、モンテッソーリ教育のプログラムを導入した保育園・幼稚園が設立されています。
モンテッソーリ教育を受けた著名人
自主性や集中力に加え、柔軟な対応力を育むとされる「モンテッソーリ教育」。時代を超えて支持されるその教育を幼少期に受けた著名人がいます。
たとえば、「アンネの日記」の著者として知られるアンネ・フランクや、Microsoftの創立者であるビル・ゲイツ、Appleのスティーブ・ジョブズ。元アメリカ大統領のバラク・オバマ、イギリス王室のウィリアム王子など、さまざまな分野を牽引するリーダーがモンテッソーリ教育を受けていたとされます。
また、日本では棋士として活躍を続ける藤井聡太名人が、幼少期にモンテッソーリ教育を受けたことで知られています。メディアで取り上げたられた後、同氏が遊んでいたスイスのおもちゃ「キュボロ」が爆発的に売れ、一時は入手困難になったほどです。
モンテッソーリ教育で重視される5つの教育分野
モンテッソーリ教育では、1つのことに夢中になり、成長したいと子ども自らが思う「敏感期」に合わせた教育を行っています。ここからは、モンテッソーリ教育で重視される5つの教育分野について紹介します。
言語教育
乳幼児期、言葉の敏感期には母国語を次々と吸収します。この「吸収する精神」は、乳幼児期にのみ存在するとされます。大人になった後の言語習得には労力がかかりますが、物事に対する興味や関心、情報を吸収する精神の有無が大きく影響しているのです。
言葉の敏感期は、0〜3歳まで継続するのが特徴で、周囲で話されている言葉を「母国語」として吸収・習得します。この時期に系統化された教具・教材に自ら興味を持ち、取り組むことで「読み書き」を自然と学んでいきます。
言葉の敏感期は、言語スキルを高めるために大切な時期です。いわば、親子の日常会話が一番大切な教具といえるでしょう。
感覚教育
言語教育と同様に、モンテッソーリ教育では「感覚教育」を重視します。これは感覚器官が発達する乳幼児期に、自分を取り巻く環境を正しく知る方法や、行動を教えるものです。記憶力や思考力、創造力を引き出し、知性を備えた人間になるための基礎作りをします。
算数教育
言葉と同じように「数」は日常に溢れています。モンテッソーリ教育における算数教育は、数量概念を身につけるため、感覚で「数」をとらえるところからスタートします。その後、棒やビーズなど、具体物で数量を学びつつ、数量を言い表す数詞や、数字ごとの関係性を一致させていきます。こうした実体験で得た数の概念は、思考の土台を築あげるのです。なお、算数教育は4歳後半から行います。
文化教育
文化教育とは、子どもの興味に合わせて変える総合学習のことです。子どもの「なぜ?」という疑問を見つけ、その答えや「なぜそうなのか?」を理解するまでのプロセスを重要視します。
これは歴史・地理・地学・植物など、小学校の社会や理科に相当する分野といえます。子どもの知りたい欲求に答え、自分を取り巻く環境や世界、宇宙へと興味の種を蒔くことが目的とされます。得意分野を深く探求させ、興味や才能を伸ばすための大切な学びです。
日常生活の練習
教育分野とは別に、「日常生活の練習」を教育の一環で実施します。これは一言でいうと、生活環境に適応するための学びです。モンテッソーリ教育における日常生活の練習は、生後6ヶ月ごろから始まり「つかむ・運ぶ・離す」という一連の動作を行うことで、知性を築き上げます。この運動により精神の発達も促進され、情緒の安定にも繋がります。
また、子どもが扉を開けたり閉めたりする動作や、物を何度も出し入れすることを大人は「いたずら」と感じてしまうことがあります。しかし、子どもはこの「いたずら」を繰り返すことによって、自分の生活環境を理解し、適応していくのです。
モンテッソーリ教育のメリット
ここからは、モンテッソーリ教育を実践するメリットをご紹介します。
個性が伸びる
日本で一般的に行われている集団教育とは異なり、モンテッソーリ教育は子どもの自由を尊重し、自発的な学びを促します。興味がある活動に好きなだけ取り組めるため、結果的に個性を引き出しやすいメリットがあります。
自主性と積極性が向上する
モンテッソーリ教育では、活動を「おしごと」と呼びます。作業内容を大人に決められることはなく、子ども自身が決めた「おしごと」を決められた時間内で取り組むことで、積極性や自主性が育まれます。
集中力が高まる
教師は特段指示をせず、子ども一人ひとりの「おしごと」を邪魔しません。夢中になれる教具とその環境により、自分自身の納得がいくまで「おしごと」に打ち込むことで、集中力や忍耐力を養います。
社会性を育める
モンテッソーリ教育を取り入れた保育園・幼稚園では、年齢や性別を問わない「縦割りクラス」を採用しています。年齢・性別が異なる子どもとの関わりにより、お互いの違いを受け入れながら同じ時間を過ごしていくのです。
これにより、年下のお世話をすることで責任感が芽生え、下の子は年上の真似をして学びを得ます。幼いうちから社会性を身につけられるのも、モンテッソーリ教育ならではのメリットです。
生涯学習の姿勢が身につく
モンテッソーリ教育は、自立した人間の育成を重視しています。責任感と思いやりを持ち、生涯学び続ける姿勢を持った人間を育てることが、本教育の理念です。子どもの自然な好奇心に応えることで、生涯学習の基礎を乳幼児期から築いていきます。
モンテッソーリ保育園を選ぶときのポイント
ここからは、モンテッソーリ保育園を選ぶ時のポイントについてご紹介します。
縦割り保育を実施しているか
モンテッソーリ教育の特徴のひとつに縦割りクラスがあります。しかしながら、0歳〜6歳までを全てひとくくりに同じクラスにしているわけではありません。一般的には、発達状況に合わせて3段階でクラス分けを行います。
モンテッソーリ教育の一般的なクラス分けは、以下の通りです。
| クラス | 年齢 | 発達段階 |
| Nido(ニド) | 0〜1歳半 | 歩行が安定するまで |
| IC(アイシー) | 1歳半〜3歳 | 歩行が安定してから |
| Primary(プライマリー) | 3〜6歳 | 3歳以降の子ども |
上記は一例であり、それぞれの保育園によって独自のクラス分けを行っている場合があります。
有資格者の先生はいるか
一部のモンテッソーリ保育園では、専門の資格を持った保育者を採用しています。資格自体は「国際モンテッソーリ協会」が発行しており、その有無に優劣はありません。ただ、モンテッソーリ教育への理解度が変わってくるため、有資格者を積極的に採用する保育園ほど、質の高い学びを得られる可能性があります。
また、モンテッソーリ教育において先生は、あくまで子どものサポート役に過ぎません。主役は子どもであり、たとえ小さくても、一人の人間として尊重するのがモンテッソーリ教育の在り方です。そのため、モンテッソーリ保育園では、大きな声で子どもに指示をしたり、怒鳴ったりする先生は見られないといいます。
適切な環境が整備されているか
適切に整備されたモンテッソーリ保育園は、清潔で物が少なく、自然豊かに感じるのが特徴です。園に足を踏み入れた時、「緑が豊か」「綺麗に整えられている」と感じた場合は、モンテッソーリ教育に最適といえるでしょう。
教具は充実しているか
子どもによって興味のあること、やりたいことは異なるため、さまざまな種類の教具が必要となります。モンテッソーリ教育を本格的に取り入れている園の場合、数えきれないほどの教具があるはずです。
モンテッソーリ教育におすすめの知育玩具5選
ここからは、モンテッソーリ教育で役立つ知育玩具をご紹介します。教具の代わりに使えるものばかりですので、ぜひ参考にしてください。
1.磁石あいうえお盤
50音が書かれた磁石と文字盤のセットです。ひらがなが書かれた文字盤に同じ文字の磁石を並べていくことで、ひらがなを覚えていきます。色々な言葉を作って遊ぶことで、モンテッソーリ教育における言語教育に繋がるでしょう。また、文字盤の裏面には数字がついており、0〜50までの数字や大小を学べます。算数教育にも役立つおもちゃです。
2.ひもとおし「どうぶつのパレード」
「ひもとおし」は、手先の器用さを意味する「巧緻性(こうちせい)」を養うおもちゃです。どうぶつによって穴の長さが異なるため、達成感を味わいながら、さまざまな難易度に挑戦できます。手のひら全体で物を握る時期から、指先でつまむことが上手になっていく時期におすすめです。アルコール消毒が可能なため、衛生的に保ちやすいのも魅力です。
3.ピエロのびっくりはかり
「ピエロのびっくりはかり」は、「軽い・重い」「数字の大小」を自分の手を使って学べる、算数教育に最適なおもちゃです。数字と重さが比例しており、手が大きい方に傾きます。「左側にかけた数字と同じ重さにするには、どの数字をかけたらよいのか」などを自分で考えることで、自然と足し算・引き算に触れられます。
4.スタッキングリング
シンプルなスタッキングリングです。大きさに合わせて積み上げていくことで、順番の概念を学べます。棒にリングを指すことで、指先の発達を促すのも良いでしょう。安全のため、真ん中の棒は折り曲げ可能です。リングの異なる色は色彩感覚も高め、感覚教育に最適とされます。リングは大きめで掴みやすく、誤飲リスクも低くて安全です。
5.木製パズル日本地図
文化教育に最適な木製の地図パズルです。地方ごとに色分けされているので、県の位置も覚えやすく、繰り返し遊べます。ピースには生息動物や名所などが描かれていて、地理以外の学びを得ることもできます。パズルピースを収納できるコンパクトな折りたたみ式で、持ち運びにもぴったりです。
モンテッソーリ教育にも使える!知育玩具はレンタルがおすすめ
子どもの自己教育力を高めるためにモンテッソーリ教育を取り入れたいなら、モンテッソーリ保育園・幼稚園に入園させるのが早いでしょう。しかしながら、近くに保育園・幼稚園がない場合や、我が子に合うか分からないと不安な場合は、自宅でモンテッソーリ教育特有の環境を作るのがおすすめです。
上記の通り、モンテッソーリ教育では教具を使用しますが、これは知育玩具で代用可能です。「具体的にどのおもちゃがいいの?」と悩んだときは、プロに選んでもらうといいでしょう。そこで便利なのが、おもちゃのサブスクです。
おもちゃのサブスク「ChaChaCha」では、2ヶ月に一回、ご自宅におもちゃをお届けします。保育士など、幼児教育のプロがおもちゃをプランニングし、お子様の成長・発達や、ご要望にマッチするおもちゃを選定します。申込時のヒアリングで「モンテッソーリ教育をしたい」とお伝えいただければ、教具の代用となるおもちゃをご提案します。
おもちゃのサブスクのメリットは多岐にわたります。たとえば、おもちゃの購入費用の節約もその一つです。モンテッソーリ教育ではたくさんの教具を必要としますが、せっかく購入しても我が子が遊んでくれるとは限りません。買いすぎておもちゃで溢れかえり、自宅のスペースがなくなるケースも見られます。
「ChaChaCha」では、必要な時期に、適切なおもちゃをレンタルできます。知育玩具をたくさん借りても返却するため、自宅のスペースを取りません。もちろん、お子様が気に入ったおもちゃはレンタル期間を延長したり、買取することもできます。2ヶ月おきに新しいおもちゃを用意できるため、成長・発達にあったおもちゃを揃えておけるのが魅力です。
まとめ
イタリアで生まれたモンテッソーリ教育は、国籍や世代を超え現在では140カ国以上で支持されています。子どもを主役にし、親はサポートに務めるこの教育法は、日本で一般的な集団教育とは性質が異なるものです。しかし、精神的に「自立した人間」を育てる上で、モンテッソーリ教育はとても有効でしょう。
家庭で実践する場合、知育玩具も活用し、取り組んでみてください。モンテッソーリ教育の実践を考えているママ・パパは、ぜひおもちゃのサブスク「ChaChaCha」を活用してみてください。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!