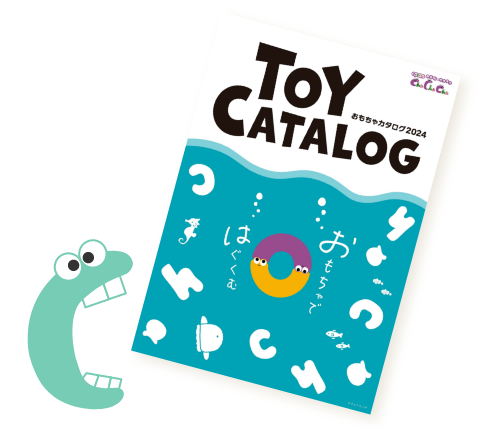子どもの発達段階と遊び|知育玩具がもたらす効果とは?
子育てにおいて気になる、我が子の発達。「○○くんよりも背が低い」「○歳になっても歩くのが苦手」など、つい他人の子と比べてしまうことも少なくありません。心理的・身体的発達は個人差が大きく、目安こそありますが、その通りに育つとは限らないのです。そこで今回は、社会的心理学の観点から、乳幼児〜青年期における子どもの発達段階をご紹介します。
子どもの発達段階とは?

文部科学省によると、子どもの発達は以下4段階に分類されます。
- 乳幼児期
- 学童期
- 青年前期
- 青年中期
発達段階は「発達段階利理論」の略称で、これまで世界中の学者が独自の心理的・身体的発達理論を提唱してきました。発達段階理論という大枠の中に、さまざまな解釈による「子どもが大人へと成長するまでのプロセス」が存在するイメージです。
各段階の詳細をお話する前に、親として知っておくべきことが1つあります。子どもの発達段階には、とても大きな個人差が生じるのです。
たとえば、文部科学省が定義する乳幼児期とは、1歳未満の子どもを指します。「○や○ができるようになる」などと、段階別の特徴や傾向に触れますが、必ずしも我が子の発達が、その定義を満たすとは限りません。極端な例を除き、発達のスピードが早い子ども・遅い子どもがいるのはごく自然なことです。
そのため、「まだ立てないけどうちの子は大丈夫……?」「○歳なのにママって呼んでもらえない」などと心配する必要はありません。
目次
エリクソンの発達段階とは?
代表的な発達段階理論に「エリクソンの発達段階」があります。「エリクソンの発達段階」とは、アメリカの発達心理学者「エリク・H・エリクソン」が提唱した「心理社会的発達理論」です。そのわかりやすさから、教育機関などで子どもの発達段階を扱う場合、同理論で説明するケースが多く見られます。
「エリクソンの発達段階」では、「ヒトの発達」を8段階に分類し、各段階において解決すべき心理的課題を提唱しています。
- 乳児期(出生から1歳年未満)
- 幼児期初期(1歳から3歳)
- 幼児期後期(3歳から6歳)
- 学童期(6歳から13歳頃)
- 青年期(13歳から22歳頃)
- 成人期(22歳から40歳頃)
- 壮年期(40歳から65歳頃)
- 老年期(65歳以上)
※資料により各段階の呼称が異なります
子どもの発達段階にフォーカスした場合、乳児期から青年期における特徴や心理的課題の把握が重要です。一部抜粋すると、乳児期は「信頼」、幼児期初期は「自立性」、学童期は「勤勉性」、青年期は「自我同一性(アイデンティティ)」が心理的課題になるとされます。
わかりやすいのは、青年期の心理的課題ではないでしょうか。通常、11~13歳の子どもは心理的・身体的に大きく成長する時期です。いわゆる「思春期」は、集団生活において問題行動を起こしたり、親に反抗的な態度を見せたりします。
理屈はシンプルで、子どもから大人へと成長すること、すなわち「自我(自主性)」を獲得しようとする際に溢れ出るエネルギーを外にぶつけているのです。思春期を経て子どもは「自我同一性を獲得」し、大人になっていきます。
子どもの発達段階の特徴と傾向
上記の通り、子どもの発達段階は「乳幼児期」「学童期」「青年期」の3つに大別されます。各段階の特徴から、子どもが大人になるまでのプロセスの全体像を把握しましょう。
その上で、子どもの発達に応じた接し方のポイントや心理的課題の解決策にも触れます。現在子育て中の方、これからお子様を授かる予定の方は、ぜひ参考にしてください。
乳幼児期

乳幼児期は、主に1歳未満の子どもが類別される発達段階です。「エリクソンの発達段階」においては、乳児期・乳児期初期・乳児期後期にあたります。
外界に出生した乳幼児は、大きな環境の変化に適応していきます。その上、著しいスピードで心身が発達し、寝る・起きる・ミルクを飲むといった生活リズムを形成。日常生活において「五感」が刺激され、およそ1年かけて自身の欲求を表現できるようになります。
欲求の表現といっても、1歳前後の子どもはまだ言葉を話すのは難しく、親との意思疎通では身体の動きや「あー」「うー」といった喃語(なんご)を使います。さらに大きく笑ったり泣いたりして、感情を表現していきます。
乳児期の心理的課題は、「愛着の形成」と「基本的信頼の獲得」です。愛着は、母親あるいは母親同等の立場の人物から愛情を注がれることで形成されます。同時に安心と、人に対する基本的信頼を得るのです。
愛着の形成は極めて重要です。たとえば、乳児期に育児放棄や虐待、無関心などで愛情を注がれずに育つと、心理的・身体的発達に悪影響をおよぼします。愛着が形成されないことで、情緒が不安定になったり、激しい問題行動を起こしたりする恐れがあるのです。乳児期で何よりも大切なのは、我が子に安心を与え、基本的信頼を得ることです。
次に、幼児期は初期と後期にわかれます。幼児期初期は1歳から3歳が目安で、急速に言語能力が発達し、行動も活発的になる時期です。自主性・主体性の形成が始まり、気に入らないことがあると感情的に怒ったり泣いたりします。いわゆる「イヤイヤ期」に相当する段階です。
後期は3歳から6歳が目安です。徐々に自立性が芽生え、物事に対して意思決定ができるようになります。遊びの系統が変化していき、「ごっこ遊び」で社会性を学びます。さらにイタズラをして親に叱られると、反発と同時に「罪悪感」を覚えます。幼児期後期は、急速に人間らしく成長する時期といえるでしょう。
学童期

6歳から13歳が目安の学童期は、生活の場が家庭から学校に変わる時期です。6年間の小学校生活を通じて社会性を身につけたり、自己肯定感や「有能感」を得たりします。
有能感とは、勉強や課題に取り組み、それをクリアすることで「自分ならできる」と思う感情の一種です。自己肯定感や、物事に真面目に取り組む「勤勉性」の形成に影響するため、いかに学校生活で有能感を得られるかが重要でしょう。
一方で、学校生活では学業や運動による競争、勝ち負けを経験します。それによって自身の得手・不得手を理解し始めるとともに、「敗北が劣等感を形成する」のです。
何らかの形で強い劣等感を得ると、自己肯定感は低下し、自分に自信を持てなくなります。しかし、人間として成長するには多少の劣等感が欠かせません。なぜなら劣等感を持つことで他人の気持ちを理解し、優しく接することができるためです。
学童期はいわば、思春期に向けた準備期間です。いかに学童期で勤勉性を身につけ、自己肯定感を高めて自信を持ち、劣等感を知って人に優しくできるかが重要となります。
青年期

13歳から22歳を青年期といいます。初期は中学校に通い始める年齢で、個人差こそあるものの、思春期が始まる時期です。発達状態は上記の通りで、「自我同一性の獲得」に向けて考え、苦しいほど悩む子もいます。問題行動に走ったり、親に暴言を吐いたりする子もいますが、本人も苦しいのです。「自分が何者なのか?(自我同一性)」という心理的課題に直面した場合、「役割の混乱」を招きます。
役割の混乱とは、「自分が何者であるのかがわからない」「何のために生まれて、何をすればいいかがわからない」という危機的な心理状態です。そのため、思春期の子どもに対しては、「認める」「受け入れる」ことが何よりも重要とされます。「自我同一性の獲得」は本人のみができ、親は見守ったり背中を押してあげたりすることしかできません。少なくとも、「ダメじゃないか」「なぜ○○なんだ」と否定的な言葉を投げるのはNGです。本当の意味で人格が形成される大切な時期であるため、親は子どもとの関わり方に、最大限配慮する必要があります。
親が子どもの発達段階を理解するメリット
ここでは、親が子どもの発達段階を理解するメリットを解説します。
円滑にコミュニケーションが取れる

3つに大別される発達段階すべてに心理的課題が存在します。たとえば、乳幼児は「イヤイヤ期」が、青年期には思春期が訪れるものです。子どもの発達段階に応じて正しい接し方を身につけておくと、円滑なコミュニケーションと良好な家族関係を維持できます。
発達に応じた課題に対処できる
上記に関連しますが、発達段階における心理的課題は、親子一緒で解決を目指すものです。乳幼児期は愛情を注ぎ、学童期には集団行動や社会生活を理解できるようサポートし、青年期には、「自我同一性の獲得」に向けて見守ったり手を差し伸べたりします。各段階の心理的課題を知っておけば、ケースバイケースで対処できるのがポイントです。そのためにも、常に子どもの様子を観察し、適時サポートすることが大切といえるでしょう。
子どもの発達と遊びの関係
子どもの心理的・身体的発達を促す方法は多岐にわたります。たとえば、「遊び」も発達を促す大切なプロセスです。ここでは、「エリクソンの発達段階」の観点から、0〜1歳にあたる乳幼児の遊びが発達に影響する理由をご説明します。具体的な遊び方にも触れますので、ぜひ参考にしてください。
遊びが子どもの発達に影響する理由
乳児期における「遊び」には、大きくわけて3つの効果があるとされます。
- 心理的・身体的能力の発達を促す
- 創造性や発想力を育む
- 自発性が身につく
幼児期における定番の遊びといえば、はじめに「ごっこ遊び」やサッカーなどのスポーツが挙げられるのではないでしょうか。「ごっこ遊び」で何者かを演じることで、創造性や柔軟性が育まれます。また、スポーツを通じて身体能力が向上し、チームプレイという名の社会性や、規律を守る意識が芽生えます。さらにいうと、「だるまさんが転んだ」などの外遊びも、子どもの発達に好影響を与えます。
外遊びで自然と触れあったり、同年代の友達や年上の子と接したりすることで、「社会で生きるための能力」を身につけます。特定のスキル・能力の発達に影響するのではなく、あらゆる能力が包括的に向上するイメージです。
また、自宅では知育玩具を使った遊びが効果的です。たとえば、パズル系やブロック系の知育玩具には、創造性・発想力・思考力を高める効果が期待できます。達成感や自己肯定感の向上、「次もやってみよう」という自発性も身につくため、非常におすすめの知育玩具です。
子どもの発達を促す方法
さまざまな形で遊ばせるのが、効率的に発達を促す近道でしょう。しかし、近年は在宅時間の増加により、外遊びの頻度が減少しています。以前に比べて「自宅で楽しめる遊び」のニーズが増えている印象も受けます。
おすすめはやはり、知育玩具です。知育玩具とは、想像力や思考力、問題解決力向上といった知育効果が得られるおもちゃの総称。通常のおもちゃとは違い、考えながら遊ぶよう設計されています。娯楽性は少ないものの、列挙した知育効果を、遊びを通じて得られるのが特徴です。
知育玩具はおもちゃのサブスクでレンタルがおすすめ!
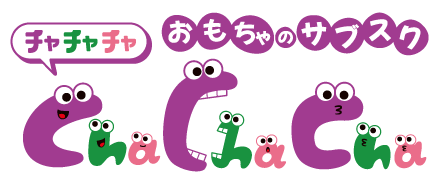
子どもの発達を促す知育玩具ですが、専門的な製品ゆえに価格設は張ります。さらに、知育玩具には対象年齢が設定されているため、いずれは対象年齢から外れるのです。誤解を恐れずにいうと、知育玩具はいずれ不要になります。
そのため近年は、「おもちゃのサブスクリプションサービス(サブスク)」で知育玩具を借りる人が増えています。数あるサービスの中で、もっともおすすめなのは「chachacha」です。
「chachacha」では、専属の保育士らがお子様一人の発達段階を考慮し、最適な知育玩具を選定。サービス利用時に行うヒアリング情報を参照するため、「本当に必要なおもちゃ」のみを厳選してお届けします。
利用方法は簡単です。公式サイトから利用申請を行い、お子様に関する方法をヒアリングシートに記入いただきます。基本プランを選択して契約が完了すれば、後日6~7点の知育玩具がご自宅に届きます。隔月で新しい知育玩具が届くため、お子様も飽きずに遊べるでしょう。おもちゃのサブスクに興味のある方は、ぜひ一度「chachacha」のサービス内容をご覧ください。
まとめ
親として、子どもの発達段階の理解はとても大切です。「親の心子知らず」ということわざがありますが、それは逆もしかり。子の心を知らなければ、円滑なコミュニケーションや親子関係の維持、ひいては「子育ての成功」につなげるのは難しいでしょう。「chachacha」が提供する知育玩具なども活用し、楽しみながら子育てに臨んでみましょう。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!