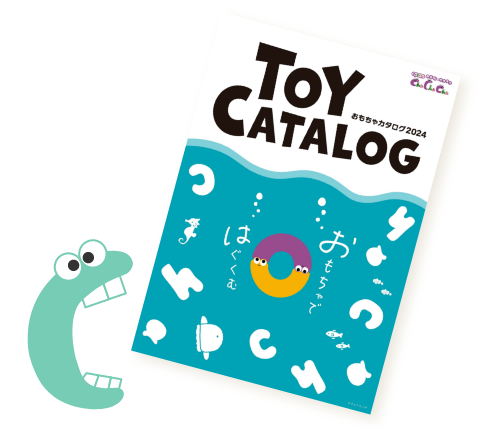赤ちゃんはいつから「つかまり立ち」ができる?練習に最適な知育玩具も紹介
首が座り、ハイハイもできるようになってきた赤ちゃんは、もう少しで1人歩きをするようになります。すぐに歩くことはできませんが、次第に座っているママ・パパの肩やベビーゲート、テーブルなどにつかまって立ち上がる練習を始めるでしょう。
そこで今回は、赤ちゃんがいつからつかまり立ちをするのか、つかまり立ちの練習におすすめの玩具や注意点などについて、詳しく解説していきます。
目次
赤ちゃんがつかまり立ちする時期は?
SNSで自分と同じように育児を頑張るおママ・パパの投稿が見られるようになった昨今、ご自身のお子さんと比べてしまう方も少なくないでしょう。
一般的に赤ちゃんは、生後11ヶ月〜12ヶ月ごろにつかまり立ちができるようになります。中には生後6〜7ヶ月でつかまり立ちを始める赤ちゃんもいます。厚生労働省(※)の調査では、1歳までに9割の赤ちゃんがつかまり立ちをしているとのことです。
一方、1歳を超えてもつかまり立ちが難しい子もいます。子どもの身体的・精神的発達は個人差が大きく、歩き始めが遅い可能性があります。親は焦らず、しっかりと我が子を見守ることが大切です。
1人歩きができるまで|赤ちゃんの成長過程
赤ちゃんの成長は目覚ましく、少し前まで寝返りも打てなかった赤ちゃんがあっという間に1人で歩けるようになってしまいます。ここでは、1人歩きをするまでの赤ちゃんの成長過程を解説します。
ずり這い・ハイハイをする
赤ちゃんは、うつ伏せから首を自分で持ち上げられるようになると、ずり這いを始めます。最初は後ろに下がってしまいますが、徐々に前に進めるようになっていきます。
生後10ヶ月前後にハイハイを始め、家中を自由に行き来できるようになります。落ちているものを拾って誤飲してしまう危険性も高まるので、注意が必要です。中にはハイハイをしないまま、つかまり立ちをする赤ちゃんもいます。
つかまり立ちをする
壁やテーブル、座っているママ・パパの肩につかまって、立ち上がるようになります。慣れるまでは、バランスを崩して尻もちをついたり、後ろに倒れてしまったりするかもしれません。まだまだ不安定な時期なので、子どもから目を離さないよう気をつけましょう。
伝い歩きをする
つかまり立ちができるようになると、伝い歩きをするようになっていきます。始めは両手で壁やテーブルにつかまって移動しますが、しだいに片手だけでも移動できるようになっていきます。キッチンなど危険が多い場所にも手を伸ばすため注意が必要です。
1人歩きをする
つたい歩きが上手になると、次第に歩けるようになっていきます。何かにつかまらないと立つことができなかった赤ちゃんも、自分一人で立てるようになります。歩くコツを掴むまで少し時間はかかりますが、毎日少しずつ歩けるようになるでしょう。
つかまり立ちが難しい原因は?
子どもの成長・発達には個人差があります。そのため、つかまり立ちを始めないことを心配し過ぎる必要はありません。
また、つかまり立ちに適した「支え」が周囲にないケースもあります。初めのうちは支えがないと立ち上がれないので、適切な練習環境を整えることも大切です。このほか、「シャッフリング・ベイビー」と呼ばれるお座りの状態で移動する赤ちゃんもいます。
シャッフリング・ベイビーの子は、うつ伏せ状態や、足が床に触れることを嫌がる傾向があります。医学的な原因ははっきりしていませんが、海外では8〜10%、日本人でも3%の子どもがシャッフリング・ベイビーといわれています。決して珍しいケースではなく、また、多くの場合2歳頃までには歩き始めます。
稀に発達障害や神経系の疾患が要因で、つかまり立ちをしない子もいますが、一般的には練習することで、つかまり立ちを促せるでしょう。
つかまり立ちの練習におすすめの知育玩具
つかまり立ちをするためには、適度な高さや支えになるものが必要です。ここからは、つかまり立ちの練習に有効な知育玩具について詳しく紹介していきます。
手押し車
つかまり立ちを始める1歳前後から使える玩具で、楽しく遊びながら歩行をサポートします。「ベビーウォーカー」や動かすと音がなる仕掛けがあるタイプもあるため「カタカタ」とも呼ばれます。手押し車は、自立歩行に必要な筋力やバランス感覚を養います。成長に合わせて組み替えることで、メリーから手押し車になるタイプの玩具もあります。
ベビーサークル
プラスチックや木製のベビーサークルもつかまり立ちの練習に有効です。サークルの高さも製品によって異なり、赤ちゃんの身長や使う月齢に合わせて選ぶことができます。サークル内におもちゃがついているタイプもあり、料理中で手が離せないときなどにも、赤ちゃんを安全に遊ばせておくことができます。
テーブルおもちゃ
テーブル板に型はめブロックや、歯車、音が鳴るボタンなどがついた玩具です。高さがあるためつかまり立ちがしやすく、練習に最適といえます。また、成長に合わせてテーブルの足を取り外せるタイプもあり、つかまり立ちを始める前のお座りの時期から使用できます。合わせて指先を使う遊びは、脳や神経の発達に効果的とされています。
つかまり立ちの練習の注意点
つかまり立ちを始めたばかりの頃は、バランスを崩しやすく危険なこともあります。ここからは、安全につかまり立ちを練習するための注意点を解説します。
練習中は側そばで見守る
赤ちゃんがつかまり立ちをしようとしている時は、必ずそばで見守るようにしましょう。転倒時に頭をぶつけたり、舌を噛んでしまったりすることもあります。上手に転ぶことができないので、すぐに手が届く距離で見守ることが大切です。
転倒対策をする
赤ちゃんの頭は重く、体重の約3割を占めるといわれています。バランスを上手に取れるようになるまでは後ろに倒れてしまうことがよくあります。つかまり立ちの練習をしている間は、転倒防止リュックをつけるなど、赤ちゃんの安全に十分配慮しましょう。また、テーブルなどの家具の角は、コーナークッションで保護しておきます。滑って転倒しないために、靴下を脱がせたりプレイマットを敷いたりするのもおすすめです。
周囲に危険なものを置かない
つかまり立ちを始めると、ハイハイやお座りの時には届かなかった高さにも手が届くようになります。テーブルの上には、タバコや灰皿、化粧品、ペンなど先の尖ったもの、コップなどの割れるものを置かないようにしてください。
また、1歳頃の子どもは、食べていいものと悪いものの区別がつかないため、誤飲リスクがあるものには触らせないよう気をつけましょう。つかまり立ちを始めるときは、周囲に危険なものがないか、よく確認することが大切です。
つかまり立ちの練習になる知育玩具は「ChaChaCha」で借りよう
つかまり立ちの時期は、1人で歩けるようになるまでのわずかな期間です。そのため、練習目的で購入した玩具が気に入ってもらえなかったり、すぐに飽きられたりすることもあるでしょう。そこでおすすめなのが、おもちゃのサブスクサービスである「ChaChaCha」です。
「ChaChaCha」は、知育玩具に特化した経済的かつサスティナブルなサブスクサービスです。本サービスでは、月額料金を支払うことで、我が子の成長・発達を促す知育玩具をレンタルできます。料金プランは4種類あり、スタンダードな基本プランは月額3,630円(税込み)で利用可能です。2ヶ月毎に成長に合わせた5〜6点の知育玩具が届きます。
プログラミングや育脳に特化した5歳児向けの「学研ステイフル監修プラン」は、月額4,950円(税込)で利用できます。また、発育が気になる赤ちゃんには、月額4,378円(税込)の「特別支援教育プラン」がおすすめです。さらに法人向けのプランもご用意しています。
ChaChaChaでは、現役の保育士や子育てのプロが知育玩具を選びます。契約時に記入いただくヒアリングシートをもとに選定するため、お子様一人ひとりに最適な玩具をお届けできます。
お子様が気に入った玩具は、特別価格で買い取ることも可能です。必要な玩具だけを手元におくことができるため、自宅のスペースを取りません。なお、破損や汚れによる弁償も一切ないので、お子様には思いきり遊んでいただけます。
まとめ
生まれた時の体重が異なるように、赤ちゃんの成長にも個人差があります。なかなかつかまり立ちをしなくても、焦る必要はありません。赤ちゃんのペースに合わせてあたたかく見守りましょう。赤ちゃんの成長に向けた手助けの一つとしてぜひ、知育玩具を利用してみてください。
おもちゃのサブスク「ChaChaCha」では、成長に合わせた玩具を2ヶ月に一度、お届します。常に新しいおもちゃに触れることで興味の幅が広がるでしょう。つかまり立ちの練習におすすめの玩具は、ぜひおもちゃのサブスク「ChaChaCha」でレンタルしてみてください。
この記事の監修者

五十嵐 麻弥子
フリーライター/上級心理カウンセラー/不登校支援カウンセラー。
出版社勤務を経てフリー編集ライターに。子育て・教育・医療・健康を中心に、さまざまな媒体で執筆多数。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!