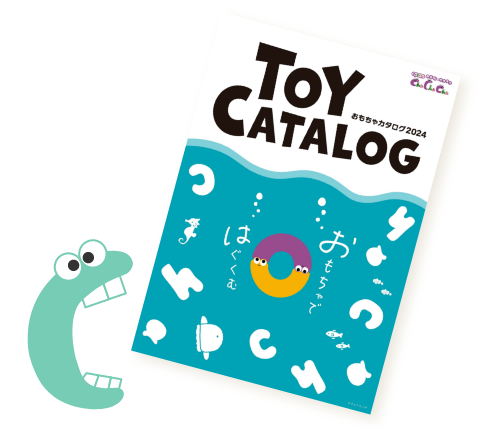知育とは?基礎知識や方法、子どもが得られる効果を徹底解説
現代の幼児教育において、「知育」の重要性が高まっています。知育とは、子どもの非認知能力を高める教育方法の一つです。近年は、雑誌などのメディアが取り上げたことで、「私たちも知育を始めないと」と思っているママ・パパは少なくありません。そこで今回は、知育の基礎概念や目的、方法、子どもが得られる効果を詳しく解説します。
知育とは?
知育とは、遊びを通じて子どもの知能・知力を伸ばす教育の総称です。幼児期に取り組むことで、社会生活を送る上で欠かせない「非認知能力」の向上につながると考えられています。子どもが楽しみながら学べる手法であり、幼稚園や保育園、家庭での教育に取り入れられています。
知育教育の方法はさまざまです。家庭では、さまざまな年齢層に適した知育玩具を使うといいでしょう。コスト面が気になる場合、後述する知育玩具のサブスクサービスを活用するのがおすすめです。
知育の目的は、子どもの興味を引く遊びや活動を通じて、非認知能力を育てることにあります。たとえば、しりとりを例にとると、どこでも手軽に楽しめる遊びであると同時に、語彙を増やす効果もあります。
さらに、知育は子どもの知能・知力に加え、コミュニケーション能力や問題解決能力を育みます。知育を通じて自身の興味や才能を認識したり、自己肯定感が高まったりすることもあるでしょう。
子どもが自然と「学びたい」と思えるような環境整備は、知育を行うとき重要になるポイントです。手が届くところに知育玩具を置く、遊びに集中できるスペースを作るなど、親ができるサポートはたくさんあります。これから知育を始めるママ・パパは、知育の基礎概念と目的を正しく理解することから始めてみましょう。
三育とは?
三育とは、知育・徳育・体育の3つをバランスよく育てることで、子どもの「生きる力」を育むという考え方です。知育は知能・知力、徳育は道徳心、体育は身体能力を高める教育のことです。今回のテーマである知育は、三育の1つに含まれています。
ここでは、知育と並ぶ徳育・体育の特徴を簡単にご説明します。
徳育
徳育とは、人間としての道徳的な考え方を育むための教育です。知育・体育とともに、教育の基礎を形成する要素となります。道徳心を持ち、豊かな人間性を養うことが目的です。
徳育では、自身の生き方を追求する力、生活習慣の確立、コミュニケーション能力や社会の一員としての責任感の育成などが重視されます。
体育
体育は、子どもたちの運動能力や健康維持、チームワークや協調性を育むことを目的とした教育です。三育では、知育・徳育・体育のバランスが重要視され、これらを均等に育てることで、子どもたちの生きる力が養われると考えます。
知育の効果とは?
知育には、思考力や問題解決力、創造力などの非認知能力を高める効果があります。具体的に向上が期待される能力について、解説していきまましょう。
論理的思考力
論理的思考力とは、物事の論点や関係性を整理して理解し、他者に説明する力です。論理的思考力が高まると、発言に説得力が増すほか、相手の感情・思考を理解しやすくなります。また、さまざまな視点から物事を見つめ、複雑な問題でも一つひとつ紐解けるようになります。日々の生活において、論理的思考力を鍛えることが、子どもの人生を豊かにするでしょう。
問題解決力
問題解決力とは、さまざまな問題に対処し、適切な解決策を見つけ出す力です。状況を正確に捉え、いくつかの解決策を考え、最適な方法を選びます。後述する創造力やコミュニケーション能力も、問題解決力と密接に関わっています。
問題解決力は、積み木やパズルといった「思考」と「選択」が求められる知育玩具で伸ばせます。自分で考え、行動する機会を増やすことが大切です。
創造力
創造力とは、アイデアや物事を生み出す力のことです。英語で「クリエイティビティ」といい、独自の発想から新しい価値を創り出します。なお、これに近い能力に発想力があります。一般的には、目に見えないものから形を作り出すのが創造力、知識や経験をもとに新しいアイデアを生み出すなら発想力が必要とされます。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力とは、家族や友達と意思疎通を図り、相互理解を深めるための力です。相手の気持ちや考えを理解し、適切な言葉や態度で伝える情報伝達力、リスニング力、表現力、説得力などが、コミュニケーション能力に含まれます。
巧緻性
巧緻性とは、手先の器用さや細かい動作を行うための能力です。近年は小学校受験などで、巧緻性を試す問題が出題されます。巧緻性を高めるには、手を使ってものを作る機会を増やすことが有効です。たとえば、絵を描いたり、粘土で形を作ったりすることで、手指の動きが鍛えられます。
知育と遊びの違いは?
「知育」と「遊び」は混同されることがありますが、目的に明確な違いがあります。まず、知育は子どもの知能・知力を伸ばすことを目的とした教育です。遊びを通じて思考力や創造力、問題解決力といった非認知能力の向上を目指します。一方、遊びにこれといった目的はなく、子どもは自由に楽しむことができます。
知育は子どもの「やってみたい」という意欲を大切にする教育です。課題に対して試行錯誤を重ね、できたときに達成感や喜びを感じられます。それが自己肯定感の形成につながり、自分に自信を持てるようになると考えられています。
もちろん、遊びの中に知育要素が含まれることもあります。しかし、知育は年齢やステップに応じた課題を設定するため、一つひとつの遊びにきちんとした意味があります。
たとえば、積み木はシンプルな玩具ですが、子どもの発想次第でさまざまな遊び方ができます。「こうしたらどうだろう?」「こんな形は作れるのかな?」と考えをめぐらせることによって、非認知能力が鍛えられます。
一方で、目的のない遊びも、自由に楽しめるという意味で子どもの成長・発達には必要です。現在子育て中のママ・パパは、知育と遊びの違いを理解し、日々の生活にバランスよく取り入れてみましょう。子どもが楽しみながら主体的に学ぶ環境を整えれば、自然と知育は成立します。
知育に科学的根拠はある?
知育は古くから行われてきた幼児教育です。その科学的根拠を裏付ける一説に、2016年にワシントン大学の児童精神科医「ジョアン・ルビー」が発表した論文があります。
人間の脳は、6歳までに約90%が完成するとされます。6歳が1つの区切りであり、生まれてから6年間で、どれだけ脳に刺激を与え、情緒的な発達を促せるかが重要なのです。
同氏が発表した論文では、6歳までに母親から愛情を受けて育った子と、そうでない子では、脳の発達に2倍近くの差があるとしています。同氏によると、母親の愛情は子どもの脳の「海馬」を刺激し、認知能力・非認知能力を高めるとのことです。ただ、重要なのは刺激を受ける頻度や強度であって、ほかの手段でも脳の発達を促すことはできます。
たとえば、知育玩具には0〜6歳の対象年齢が設定されています。年齢や発達に適したおもちゃで遊ばせると、海馬に刺激が与えられ、子どもの成長・発達をが促されます。子どもの脳の発達を促し、非認知能力の向上を図るなら、できるだけ早く知育に取り組むとよいでしょう。
代表的な知育の方法
知育にはさまざまなアプローチがあります。ここでは、代表的な知育の方法を3つにわけてご紹介します。
知育玩具を使う
スタンダードな知育の方法であり、知育教育ともいいます。一般的に知育玩具は、非認知能力の向上を目的に設計・開発されています。個人差はあるものの、知育玩具で遊ばせることで、さまざまな非認知能力の向上が期待できるのです。
たとえば、積み木や粘土などの知育玩具は、子どもが主体的に考え、創造する体験ができるおもちゃです。思考力や発想力、創造力、問題解決力を鍛えるのに、うってつけのおもちゃといえるでしょう。
また、音が鳴る楽器のおもちゃは、聴覚や視覚などの五感を刺激します。お絵かきセットなどの知育玩具で遊べば、色彩感覚が身につくでしょう。
このように、遊びを通じて向上する非認知能力は、知育玩具ごとに異なります。知育玩具を選ぶ際は、子どもの年齢や発達に合わせて選ぶことが大切です。「その都度新品を買うのは大変」と思ったら、後述する「おもちゃのサブスク」でレンタルするのも一つの手でしょう。
知育アプリを使う
幼児や子どものために開発されたスマートフォン・タブレット向け学習アプリです。知育玩具のデジタル版といえばわかりやすいでしょう。五感を刺激する幼児向けのアプリもありますが、多くは小学校低学年向けです。0〜6歳のお子さんを育てている場合は、知育玩具で遊ばせた方が効果的かもしれません。
知育教室に通う
家庭内で知育を実践するのが難しい場合、知育教室に通うのも1つの手です。知育教室は、子どもの興味や発達に応じて選びましょう。まずは体験教室に足を運び、授業内容やその場の雰囲気を確かめるのがおすすめです。
知育玩具をレンタルするなら「ChaChaCha」
「知育玩具は高いので買えない」「買い替えの頻度が高すぎる」と悩むママ・パパは多いようです。事実、新品の知育玩具は思いのほか高価で、その都度買い換えると経済的負担は避けられません。そこでおすすめしたいのが、知育をレンタルできるサブスクサービスです。
「ChaChaCha」は、カタログから好きなおもちゃを選んで借りられる、コストパフォーマンスが自慢のおもちゃのサブスクです。一番人気の「基本プラン」では、月額3630円(税込)で5〜6点の知育玩具をレンタルできます。1日あたり117円で、定価15,000円相当のおもちゃが届く、人気のサービスです。
利用も簡単です。4つの料金プランから1つ選び、公式サイトのヒアリングフォームに必要な情報を入力し、契約します。申し込み完了後、10日前後でおもちゃが届きます。交換時期が近づいたら、新しいおもちゃが自動的に届くので便利です。
まとめ
家庭内で知育を実践するなら、その基礎と正しい知識を理解しておくことが大切です。「何のための知育なのか?」「どんな効果があるのか?」「子どもにとって有益なのか?」がわかれば、上手な知育を行えるでしょう。「ChaChaCha」などのサブスクサービスも活用し、玩具を使った知育にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者

五十嵐 麻弥子
フリーライター/上級心理カウンセラー/不登校支援カウンセラー。
出版社勤務を経てフリー編集ライターに。子育て・教育・医療・健康を中心に、さまざまな媒体で執筆多数。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!