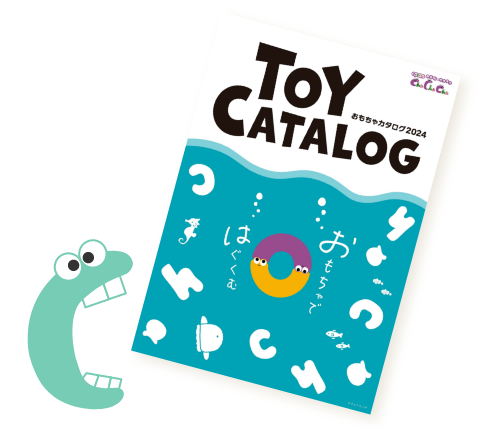三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説
三歳頃は「イヤイヤ期」や「反抗期」と言われる時期でもあります。ハッキリと自我が形成されるこの時期は、子どもとの向き合い方で悩むママ・パパが少なくありません。
今回は、「第一次反抗期」と呼ばれる三歳頃に、親として何を知っておくべきか、どのように対応すればいいのかを解説します。三歳児の平均的な身長と体重、さまざまな能力の発達、そしてイヤイヤ期や反抗期の対処法を見ていきましょう。
三歳児の成長・発達の目安
ここでは、三歳児の平均的な身長と体重、さまざまな能力の発達について解説します。子どもの成長は個人差が大きいため、いずれも参考程度に留めてください。
身長と体重
日本赤十字社などの調査によると、三歳児の平均的な身長および体重は、次の通りです。
| 三歳児の平均身長・体重 | ||||
身長(男の子) | 身長(女の子) | 体重(男の子) | 体重(女の子) | |
0ヶ月 | 93.3cm | 92.2cm | 13.7kg | 13.1kg |
1ヶ月 | 94cm | 95.8cm | 13.9kg | 13.3kg |
2ヶ月 | 94.6cm | 93.5cm | 14.0kg | 13.4kg |
3ヶ月 | 95.1cm | 94.1cm | 14.2kg | 13.6kg |
4ヶ月 | 95.7cm | 94.7cm | 14.4kg | 13.8kg |
5ヶ月 | 96.3cm | 95.3cm | 14.5kg | 13.9kg |
6ヶ月 | 96.9cm | 95.9cm | 14.7kg | 14.1kg |
7ヶ月 | 97.5cm | 96.5cm | 14.8kg | 14.3kg |
8ヶ月 | 98cm | 97.1cm | 15.0kg | 14.4kg |
9ヶ月 | 98.6cm | 97.7cm | 15.1kg | 14.6kg |
10ヶ月 | 99.1cm | 98.3cm | 15.3kg | 14.8kg |
11ヶ月 | 99.7cm | 98.9cm | 15.4kg | 15.0kg |
参考:男の子の平均身長と低身長のめやす(-2SD)
女の子の平均身長と低身長のめやす(-2SD)
子供の年齢別平均体重(男子)3才(乳児)
子供の年齢別平均体重(女子)3才(幼児)
三歳の男の子の場合、平均身長は0ヶ月で93.3cm、11ヶ月で99.7cmです。1年間で身長は、おおよそ6cm伸びる傾向にあります。対して三歳の女の子の平均身長は、0ヶ月で92.2cm、11ヶ月で99.7cmです。男の子同様、1年間で身長が約6cm伸びるとされます。
体重についても、男女の平均値に大きな差はありません。三歳の男の子の平均体重は、0ヶ月で13.7kg、11ヶ月で15.4kgとなります。1年間でおおよそ1.7kg増加する計算です。女の子は、平均体重が13.1kgから15kgと、約1.9kgの増加が見込まれます。
身体的発達
一般的に三歳児の身長と体重は、生まれたときの約4倍になります。身長の伸び方は1~2歳時代と同程度ですが、その代わり筋肉がよく発達します。1〜2歳に比べて全身のプロポーションが整い、子どもらしい体つきに変化します。
どうしても気になる親御さんは、母子手帳などにある「成長曲線」を使ってみましょう。現在のお子様の身長・体重をグラフに記載すると、成長度合いが一目でわかります。
グラフの灰色部分には、その年齢の約9割の子どもが入ります。つまり、エリア内に測定値が入れば、適切に成長していると判断できます。なお、これらの数値はあくまで平均値であり、個人差があることを念頭に置いてください。
運動能力
三歳児は男女問わず、運動能力が大幅に向上します。この段階の子どもたちは、筋肉量の増加にともない、身体を自由に動かせるようになるのです。
たとえば、三歳頃から片足で「ケンケン」したり、少し高いところから飛び降りたりできるようになります。これは適切な筋肉がつき、身体コントロールが上手になっている証拠です。また、運動を介して子どもたちは、日常の基本動作に磨きをかけます。立ち上がる・走る・跳ぶ・投げるなどの動きが、よりスムーズになるでしょう。
三歳は運動能力においての分岐点ともいわれます。この時期の運動量は、数年後の成長・発達に大きく影響するといわれています。
三歳頃は脳や神経系、非認知能力が著しく成長する時期です。運動が脳や神経系に刺激を与え、効率的な成長・発達を促します。さらに運動量が増えると、全身のバランス感覚が鍛えられます。
このことから、三歳児の子育てでは、運動能力を高めるための「遊び」を用意することが大切です。
言語能力
三歳児は物体の色や大きさを把握し、言葉で表現する力がつきます。加えて、日常で頻繁に用いる動詞を理解し、自身あるいは他人の年齢や名前などの質問に答えられます。
これまでと違うのは、言葉を用いて自分の状態を伝えたり、基本的なコミュニケーションを取れるようになったりすることです。話す言葉が約500~1,000語まで増え、「3語文」を話します。
3語文とは、「ママ おもちゃ 遊ぶ」など、3つ以上の単語を組み合わせた言葉のことです。成長とともに接続詞や助詞を覚え、徐々に長い対話が可能になります。
話すだけでなく、言葉の理解力も増します。子供たちは大人の会話に自主的に耳を傾け、その内容を理解しようとするのです。反対語や動詞の別の言い方も学び始め、より精度の高い質問に答えられるようになります。
合わせて知能的発達も進みます。たとえば、物体の数・形・大きさを認識し、その特徴や違いを言葉にできます。
精神的発達
三歳児の精神的発達には、いくつかの特徴があります。第一に、物事への興味が広がり、知的好奇心が芽生えます。その中でも、物事への「疑問」を抱くのが大きな変化といえるでしょう。
二歳から六歳頃の子どもは、大人に対して「なぜ?」「どうして?」と問う機会が増えます。心理学では「質問期(なぜなぜ期)」といい、子どもの知的好奇心や学習意欲が高まる時期です。
この時期は、何度も同じ質問を繰り返すため、困ってしまうママ・パパも少なくありません。しかし、子どもの思考力や問題解決能力が育まれる時期と捉え、適切に対応することが重要です。
「エリクソンの漸成的発達理論」によると、三歳児は幼児期初期に当たるとのことです。言語能力の急速な発達にともない、自分で物事を決めたり、行動したりする期間に入ります。この時期に、自主性と主体性の基礎が築かれるのです。
また、三歳児は自己主張が強くなると同時に、自分以外の他者に対する思いやりが芽生えます。イヤイヤ期が持続するケースもありますが、長びいても四歳頃までには落ち着いてくることが多いでしょう。
コミュニケーション・社会性の発達
三歳になると、コミュニケーション能力や社会性の基礎が身につきます。この年齢の子どもは、自身の感情だけでなく、ほかの人々の気持ちも理解し始めます。感受性が高まり、他人を思いやったり配慮したりできるようになるのです。
ポイントは、ママ・パパへの「愛着形成」です。親との間に信頼を感じると、子どもはその影響で思いやりを持ち始めます。親が示す思いやりを模倣し、他者にも同じく接することができます。
また、三歳ごろになると友だちと遊ぶ時間が増えます。遊びは、社会性を身につける大切なプロセスです。家庭ごっこや商店ごっこなど、「ごっこ遊び」を通じて人の立場や役割を学んでいきます。
三歳児の成長・発達を促すコツは?
三歳児の成長・発達を促すコツは、大きくわけて4つあります。二歳頃からイヤイヤ期が継続している場合は、その対応もしっかりと考えましょう。
親子間のコミュニケーションを増やす
親子間のコミュニケーションにより、言語能力の発達が期待できます。子どもとたくさん会話したり、一緒に遊んだりするだけでも十分です。単純ですが、親ができるもっとも大切なことといえるでしょう。
たとえば、意識的に質問を投げかけてみてはいかがでしょうか。「どっちが好き?」「どうしたい?」などと質問することで、物事を考える力や、自分の言葉で伝える力が養われます。
また、絵本の読み聞かせもおすすめです。絵や物語に触れることで、語彙と想像力が鍛えられます。絵本から多くの言葉や表現を学んで吸収し、自分のものにしていくのです。
コミュニケーションをとる上で注意すること
コミュニケーションで注意したいのは、子どもの話を最後まで聞くことです。親がしっかりと「傾聴」することで、自分の気持ちや意見が大切にされていると感じます。その結果、自己肯定感が育ち、自身を持てるようになります。
また、途中で子どもの話を遮ったり、頭ごなしに否定したりするのはNGです。言葉は上手に発せませんが、「自分の意見は尊重されない」「わかってもらえない」と、子どもなりにショックを受けるでしょう。
集団生活を経験させる
幼稚園・保育園での集団生活により、子どもは協調性や社会性、コミュニケーション能力を身につけます。特に大切なのが、子ども同士の関わりです。友達と会話したり、がんばって物事に取り組む姿に刺激を受けたりして、自分も努力しようと思うようになります。同年代の子や先生との関わりは、社会性を身につける上で欠かせません。
イヤイヤ期は適切に対応する
多くの場合、イヤイヤ期は三歳頃に落ち着きますが、持続する子も少なくありません。終わりが見えずに困り果てるママ・パパがいるのも事実です。
しかし、子どものイヤイヤ期は、人として成長するための大切なプロセスです。適切に対応することで、自己肯定感などの精神的発達を促せます。
まずは子どもの気持ちを受け入れ、子どもの意見をしっかりと聞きましょう。イヤイヤ期の子どもは、自分の考えを上手に伝えられず、そのストレスで「癇癪(かんしゃく)」を起こすこともあります。「ママ・パパにわかってもらえない」ことが最大のストレッサーであるため、子どもの声に理解や共感を示すことが大切です。
幼児教育の活用
幼児教育は、非認知能力を育むために欠かせないものです。非認知能力とは、記憶力・想像力・思考力・問題解決能力・社会性など、数値で表せない人間的な能力をいいます。学習では身につかない力のため、未就学児における幼児教育の重要性が高まっています。
家庭で幼児教育を行う場合、子どもが好きなことや興味を持っていることに集中できる「環境」を用意してください。三歳児の場合、知育玩具による遊びを通じて、非認知能力を伸ばしていくことができます。
幼児教育の一種「知育」とは?
知育とは、子どもの非認知能力を高める教育の一種です。知育玩具や教材を活用し、遊び方を通じて思考力や問題解決能力などを養います。
知育効果については、多くの研究でその有効性が認められています。たとえば、2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授の調査によると、知育を受けた子どもは六歳時点でのIQが高くなることがわかりました。
三歳児は身体的・精神的発達が著しい時期です。成長期であるため、知育の効果をより実感しやすいでしょう。
三歳児の子育てに関するQ&A
ここでは、三歳児の子育てに関する定番のお悩みと、その解答についてご紹介します。
イヤイヤ期・反抗期にどう接していいかわからない
イヤイヤ期・反抗期には、第一に子どもの気持ちを受け入れ、肯定することが大切です。仮に無理な要求であっても、一度は受け入れる姿勢を見せましょう。また、替わりの案や選択肢を与え、冷静に対応しましょう。親のポジティブな声かけが何よりも重要です。
しつけがうまくいかない
三歳児のしつけがうまくいかない場合、まずは「絶対にしてはいけないルール」を子どもと決めます。日常生活においては、ルール違反をしたときだけ叱るようにしましょう。
また、子どもに注意する際は、目線を合わせて落ち着いた声で話すことが大切です。いい行動は積極的に褒め、「自分でできた」「褒められたから頑張ろう」という気持ちを持たせてあげましょう。
体力がありあまっている
体力がありあまり、お昼寝しなかったり、就寝時間が遅くなったりする子がいます。日中は追いかけっこなどの全身運動で遊び、心地よい疲れで眠りやすくすることを心がけます。この時期は特に、ストレス解消に繋がったり、筋力やバランス感覚を鍛えたりできる遊びがおすすめです。なお、室内で遊ぶ場合は、騒音や安全面には配慮してください。
周りの子に比べて発達が遅く感じる
成長・発達は個人差が大きいため、基本的に心配は要りません。ただし、我が子の成長をサポートするため、親ができることはたくさんあります。積極的にコミュニケーションをとる、一緒に楽しく遊ぶなど、日常の中でできることを心がけるとよいでしょう。
集団生活が苦手
集団生活が苦手な理由として、自己中心性や母子分離不安などが考えられます。子どもに最適な環境が用意する、より小集団での活動を試す、自己主張と協調性のバランスを学ばせるなど、複数の対処法があります。
三歳児の成長・発達を知育玩具でサポートしよう
三歳児の子どもは、話す言葉が増え、遊びに対する興味も一気に広がります。しかし、興味はすぐに移り、新しい玩具にも飽きることが少なくありません。そこでおすすめなのが、知育玩具のサブスクリプションサービスである「ChaChaCha」です。
「ChaChaCha」は月額3,630円(税込)から利用できるおもちゃのサブスクです。お子様の成長段階や興味に合わせ、幼児教育のプロが選んだおもちゃが定期的に送られてきます。
サブスクなので基本はレンタルです。しかし、お子様が気に入ったおもちゃは、特別価格で購入できます。玩具が壊れても原則、弁償はありません。破損などを心配せず、思う存分遊ばせてあげられるのが魅力です。必要な時に必要なおもちゃを用意できるため、自宅の収納スペースを取らないのも大きいでしょう。
「ChaChaCha」の新規契約は、公式サイトからお申し込みください。料金プランや申し込み手順、利用メリットなどの解説もあります。ぜひ参考にしてください。
まとめ
三歳児の成長・発達は多面的で、それには親のサポートが欠かせません。特にイヤイヤ期や反抗期は、親子関係を深め、子どもの成長を促すチャンスです。適切に対応し、子どもの健やかな成長を導きましょう。
この記事の監修者

五十嵐 麻弥子
フリーライター/上級心理カウンセラー/不登校支援カウンセラー。
出版社勤務を経てフリー編集ライターに。子育て・教育・医療・健康を中心に、さまざまな媒体で執筆多数。
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!