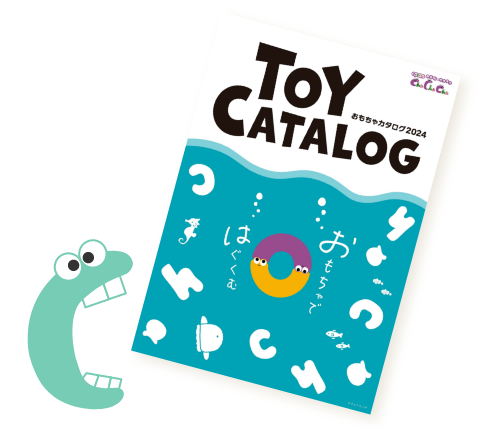お手伝いは子供の成長に良いことがいっぱい!手間なくできる事例を紹介
お手伝いは、子供の成長と自立につながるのでやって欲しいですよね。しかし実際にやってもらおうとすると、余計に手間がかかったり、時間と労力が必要だったりして、なかなかさせてあげられなかったりします。お手伝いをやらせてあげたいのに、やらせてあげられないなんてことも…。
今回はそんなお子さんのお手伝いについて、お手伝いの種類やお手伝いをしてもらうときのポイントを事例を交えて解説していきます。
またママ・パパが無理なくお手伝いさせてあげられる種類についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
子供のお手伝いは何歳ころから?
一般的には、だいたい1~2歳くらいからお手伝いを始めることが多いです。親のやることに興味を持って、よくマネをしたがるようになったら始めどき。
マネっこして洗濯物をたたもうとしたり、掃除機を持ちたがるようになってきます。こうしたマネっこをよくやりはじめて、子供が一緒にやりたくなってきたらスタートしましょう!
特に2~3歳は好奇心旺盛な時期なので、なんでも自分でやりたがります。ただイヤイヤ期も重なるので上手くいかないことも多いです。癇癪も激しくなるのでママ・パパは大変になりますが、ここは成長しているんだと考えて大きく構えていきましょう。
お手伝いは長期戦です。長い目で見ていきましょう!

【年齢別】代表的なお手伝いとの段階の目安
年齢 | 代表的なお手伝い | 目安 |
1~2歳 | いちごを洗う、玉ねぎの皮むき、テーブルを拭く | 簡単にできるもの |
3~4歳 | 配膳、食器洗い、洗濯物たたみ | 遊びの一部としてお手伝いする |
5~6歳 | 火を使った料理、お風呂掃除 | 火や家電などの道具を使うもの |
7~8歳 | おつかい、得意な家事 | 子供ひとりに任せられるもの |
参考:「キッズデザイン製品開発支援事業(経済産業省)」子育て住宅調査より
モンテッソーリ教育のなかでは、子供がお手伝いをしたがる時期がある!?
幼児教育で有名なモンテッソーリ教育のなかでは、子供が「お手伝いしたい」という時期がしっかり位置付けられています。子供が「お手伝いしたい」と言ってくるのは、社会的行動を身につけるための敏感期のひとつ、だそうです。
この時期はお手伝いをしてもらうのにピッタリ!ぜひ、お家でも積極的にお手伝いさせてあげましょう。
とはいっても、まだ2,3歳の小さな子供に料理を手伝ってもらうと、水をこぼしてしまったり、お米や小麦粉をこぼして余計に大変なことになることも多いですよね。ママ・パパとしてはやらしてあげたいけど、手間がかかってしまうので「ダメ」「見ててね」と言ってしまうのが現状でしょう。
しかし子供は、親がやっていることをしたい、お手伝いしたいという気持ちを「ダメ」と否定され続けてしまうと、その気持ち自体もなくなってしまいます。将来「お手伝いをしてくれない」ことにもつながってしまうので注意が必要です。
そうならないためには、子供の「お手伝いしたい」という気持ちを大事に受けとめてあげることが大切です。まずは気持ちを大切に育ててあげることを1番に考えてあげましょう。
正直、子供にお手伝いしてもらうのは大変…
子供たちが作ってみたい!というのでコストコで買った50個作れるチョコキットで簡単バレンタイン💝のつもりが子供らとだと簡単な作業もイライラ😂洗い物もいっぱい出るし💦意外とめんどかった🥺まあラッピングとかも全部入ってて楽は楽だったが☺普段からお手伝いとかしてる子なら1人でも作れるのかも
— もやこ>ω</ (@morsepyon) February 13, 2024
今朝子供らがおかいつを見てる間にトイレ掃除だけしとこうと思いしてたら、娘に見つかり娘もやる!と言われ、みるみる余計な仕事を増やされイライラしてしまった。
お手伝いを穏やかに受け入れられる母でありたいのに、、— どら🍁3y+1y☀️ (@yyyuyyy_ike) September 21, 2023
お手伝いしてくれるのは嬉しいけど、綺麗にしようとしたところを、余計な仕事を増やされてしまうと大変ですよね。
あるアンケート調査によると、あえてお手伝いさせていないママ・パパもいるようです。お手伝いさせない理由としては、
①親がやった方が早いから
②子供が上手にできないから
③教えるのが面倒だから、というものでした。
出典:「キッズデザイン製品開発支援事業(経済産業省)」子育て住宅調査より
ママ・パパの時間がたっぷりあれば、お子さんのお手伝いにもじっくり付き合ってあげられますが、そうもいきませんよね。共働きの家庭やワンオペで子育てしている家庭では、仕事と家事育児で忙しくそんな時間も取れないと思います。
お子さんにお手伝いをしてもらうには心と時間に余裕が必要です。時間のかかりそうなこと、汚しそうなことなどは休日の時間のある日にやってもらいましょう。
ただ、少しの手間だけであまり時間がかからないお手伝いもあります。平日はちょっとのお手伝いをしてもらいましょう。
【年齢別】ママ・パパの手間がかからないお手伝い
ママパパが無理なくできるお手伝いを年齢別にご紹介します。
あまり時間もかからず、余計な掃除や洗い物が増えないものなので、仕事で忙しい平日のお手伝いに活用してみてください。
年齢 | ママ・パパの手間がかからないお手伝い | メリット |
1~2歳 | ・食べる前にテーブルを拭く ・カトラリーを並べる ・ゴミ拾い ・ハンカチ、タオルをしまう | 小さい子でも一緒にできて、失敗も少ないです。 ゴミ拾いが得意な年齢なので、いっぱい拾ってもらって 部屋をきれいにしてもらいましょう。 |
3~4歳 | ・洗濯物(タオルなど)をたたむ ・食べた後の食器を運ぶ ・レタスやキャベツをちぎってもらう ・野菜の皮むき(玉ねぎなど) ・靴をそろえる | 簡単なものなら上手にたためるようになってきます。 ママ・パパと一緒にできて、 短時間で終わる作業をやってもらいましょう。 |
5~6歳 | ・郵便物、新聞のチェック ・カーテンの開け閉め ・野菜を洗う | 少しひとりでもできることが増えてきます。 野菜を洗うときも、水遊びにならなくなってくるので できるようならお願いしてみましょう。 |
7~8歳 | ・ごはんの配膳 ・卵を割る ・ごはんをよそう | ひとりでお手伝いができる時期です。 お家の戦力として、手伝ってもらえます。 ママの家事時間を減らしてくれるでしょう。 |
上記の例を参考に、ご家庭にあったお手伝いを探してみてくださいね。
子供がお手伝いで得られる6つのメリット

これまにあげたお手伝いは、子供の成長にメリットがいっぱいです。特に効果の高く感じられているメリットは5つあります。
①親子のコミュニケーションになる(※1)
②責任感が育つ(※1)
③自己肯定感が育つ(※1)
④自立的行動習慣が身につく(※2)
⑤探求力が身につく(※2)
大きくなってからも大切な能力ばっかりです!
青少年の体験活動等に関する意識調査(令和元年度調査)〈令和3年3月発行〉 | 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 (niye.go.jp)(※2)
親子のコミュニケーションになる
一緒に家事をしたり、お手伝いのやり方を教えたりするので、自然とコミュニケーションが多くなります。
アンケートでも親御さんの最も多くがお手伝いのメリットとして挙げていました。
いまは共働きの家庭が多く、平日に子どもとの時間がなかなか取れなくて悩んでいる人も多いでしょう。お手伝いは、そんな子どもとのコミュニケーションに一役買ってくれます。
コミュニケーションは時間以上に質が大事です。お手伝いを通して話したり、スキンシップを取ったり、時には遊んであげることで、子どもの心が安心して、満たされて成長していきます。ママ・パパとの信頼関係も築いていくことができます。
責任感が育つ
お手伝いをしてもらうと、実体験として責任感を持たせることができるので責任感が育ちます。お手伝いを任されるというのは、ママ・パパに頼りにされている証しです。家族の一員として、お家の仕事を任されると子どもは「これは自分の仕事」と思って頑張ってやろうとします。
自分の言葉や行動に責任をもって、最後までやり遂げようとする力は社会生活のなかでとても大切です。人との信頼関係を築くなかで必要な力なので、学校生活でも、友人関係でも、大人になってからも重要になってくる力がお手伝いで育まれていきます。
自己肯定感が育つ
自己肯定感とは、自分の良いところも、悪いところも全てあわせて「好きでいられる」感覚のことをいいます。
ママ・パパの前でどんなに泣いても、暴れても、決して見捨てられずに受け入れてもらえるとわかると、子どもは「自分は愛してもらえる価値がある」と思えるようになるのです。
お手伝いでいえば、卵がキレイに割れた、タオルを全部たためたなど、達成感を得られることがたくさんあります。けれど、はじめのころは上手に出来なかったり、こぼして汚してしまったり失敗も多いです。出来なくて癇癪を起してしまうこともあります。
そんなときに、親から「大丈夫だよ」「失敗してもいいんだよ」と受け入れてもらえる、認めてもらえる。上手にできたときは「上手にできたね」「ありがとう」と褒められて、感謝を伝えられることで自己肯定感が育まれます。
また少し難しいことは親が手伝ってあげて、最後の仕上げを子どもにさせてあげるだけでも達成感につながるので、おすすめです。
自立につながる
自立とは、自分でできることは自分ですること。自分の考えをもって、自発的に行動できることを指します。
お手伝いを通して、今までは親がやっていたことを自分でできるようになります。食べた食器を片づけたり、自分の服をしまったり、自分の身の回りのことができるようになるので自立につながります。まずは自分の身の回りのことからはじめて、いろんなお手伝いを経験させてあげましょう。
また家事のやり方も最初はママ・パパに教えてもらった通りにやっていきますが、何度もやっていくうちに子どもなりに考えて、「こうした方がいいんじゃないか?」と思うことが出てきます。自分の頭で考えることも立派な自立です。
探求心が身につく
新しいことに興味を持ち、創意工夫していく力が身についていきます。お手伝いは子供にとって新しいことの連続です。普段の遊びや行動のなかでは経験しないことができます。大人の世界を体験しているのかもしれませんね。
またお手伝いは失敗することも多いです。その失敗の原因は何か?ママやパパのように上手にできるようになるにはどうしたら良いか?と子ども自身で考えていきます。
何に興味を持って、子ども自身でよく考えるようになるかは、その子ひとりひとりによってバラバラなので、親御さんはそこをサポートしてあげましょう。
【お手伝い実例】先輩ママたちは、どんなお手伝いをさせている?
子供にどんなお手伝いをさせたら良いか悩みますよね?先輩ママたちはお子さんにどんなお手伝いをしてもらってるのか見てみましょう。
子供と一緒に料理
あと最近長男は料理のお手伝いがしたくて、ご飯盛ったり卵割ったり混ぜたり…色々してくれる。夫が料理全く出来ないから子供たちにはある程度出来るよう、どんどんお手伝いしてもらおうと思っている!
— あい❁4y🧒🏻+2y👦🏻+1m👶 (@mtakttktk99) March 30, 2024
賛否両論ありそうだけど、料理するとき最近子供と一緒にしてる
前からお手伝い(ゆで卵の殻むく)とかはたまにやってもらってたけど、火を使うと熱いとか油ははねて危ないとかをちょっと遠くから見てる
ご飯もたまに自分でついでる
包丁とかはまだ触らせない— だぁ@(o・ω・o)🦍🦍 (@hage749) September 8, 2023
料理のお手伝いでは、材料をこねる、混ぜるといったところから、野菜を洗ったり、卵を割ったり、お米をといだりする作業をしてもらっているご家庭が多いです。親が危ないと思う、包丁を使う調理や火を使う調理は6歳以降から始める人が多いようですね。
料理のお手伝い例
・野菜を洗う
・食材の下処理(すじとり、皮むき、種取り、ちぎる)
・お米を研ぐ
・ご飯をよそう
・かき混ぜる
・卵を割る
・包丁を使って切る
・火を使った料理
・食器を運ぶ
・食器洗い、など
Instagramでは、「台所育児」をやっているよ~という投稿も多くあがっています。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
料理はやることがたくさん!洗ったり、お米を研いだり、牛乳を測ったり、卵を割ったり、と子供にとって新感覚のことばかり。指先も手の力もたくさん使うので良いことばっかりです。
Instagramでは「台所育児」についての発信が多くあがっているので、気になった方はみてみてくださいね。
お掃除
この投稿をInstagramで見る
一生懸命、床を拭いてくれてる姿もかわいいですね。前やった時はできなかったのに、今回はできた!などお手伝いしてもらったことで子供の成長が見れるのも嬉しいですね。
お掃除のお手伝い例
・ゴミ箱にごみを捨てる
・ゴミの分別
・おもちゃの片づけ
・お風呂掃除
・トイレ掃除
・シンクの掃除
・掃除機掛け
・モップ掛け
・鏡拭き、など
掃除のお手伝いは意外と力仕事だったりします。雑巾がけや雑巾をしぼるなど、普段やらない動作ができるところも良い点です。
洗濯物
ここのところ毎日、
洗濯物をたたむお手伝いをしてくれる
2歳息子👦(写真はパジャマ)タオルはもちろん
保育園のエプロン、
1歳娘の服までも…!👶🌸最近ではハンガーを外すところから
黙々とやってくれて
決めゼリフは
「ぼくにまかせて!」天使かな😇 pic.twitter.com/0DKFLIjqpp
— あ め の@年子育児格闘 (@amenohosomichi) June 28, 2019
保育園で自分が使うものは自分でたたむ。「自分のことは自分でやる」ことの第一歩ですね。
洗濯物のお手伝い例
・洗濯物を干す
・洗濯物をたたむ
・収納場所にしまう
・しわ伸ばし
・毛玉とり
・靴洗い、など
その他のお手伝い
洗車など
この投稿をInstagramで見る
車の洗車は水遊びの要素もあって楽しいですね。アワアワを触ったり、シャワーで流したり、小さい子でも楽しくできることがたくさんあります。
その他のお手伝い例
・花に水をあげる
・草取り
・車の洗車
・郵便物を取ってもらう
・ペットのエサやり
・おつかい、など
うちの子にはどんなお手伝いをしてもらったらよいんだろう?SNSでは1歳でこんな料理までさせてるの?と悩んだり、焦ってしまうかもしれませんが、難しく考えなくて大丈夫ですよ!
上に書いた例をみると、普段やっている家事はすべてお手伝いになる、ということがわかります。ママ・パパが普段やっている家事を作業ごとに細かくわけて、簡単なものからお願いしてみましょう。
子供をやる気にさせるコツ

子どもがお手伝いを進んでやってくれるようにためにできる工夫をご紹介します。
子供専用の道具を用意してあげる
子供専用のグッズ、「マイ○○」というものを用意してあげると子どものやる気がアップします。自分専用のアイテムがあると子どもは喜びます。購入しても良いですし、親御さんが作ってあげたり、子供と一緒に作るのも楽しいですね。
花の水やり用の「マイジョウロ」はペットボトルのキャップに穴をあけるだけで簡単にできます。ペットボトル本体に色を塗ったり、絵を描いていくと愛着も湧きます。
子供用の包丁やエプロン、掃除道具などもあると積極的にやってくれるかもしれません。
お手伝い表の活用
この投稿をInstagramで見る
お手伝い表を作って、子供のやる気をアップさせているご家庭も多くいらっしゃいます。お手伝い表の良いところは、お手伝いしたことがハッキリとわかることです。親御さんもわかりやすいし、お子さんも次に何のお手伝いをするか明確なので取り組みやすくなります。
またお手伝いが終わったらシールを貼ったりすることで、達成感も感じられて、次につながるのもメリットです。
声かけを工夫する
子供にただ「手伝って」というだけではなく、「お手伝いをすることで、こんなに良いことがあるよ」「ママとパパが助かるよ」ということを伝えると、子供のやる気が出やすくなります。
またお手伝いしてくれることが、どういう理由でやっているのか、何の役に立ってるのかなど伝えていくと、ひとつひとつのことに意味があることに気付ける良い機会になります。
例えば、ごみの分別はなんのため?おもちゃを毎回片付けるのはどうして?洗濯物をモノごとに分けているのはどうして?など、子供が疑問に思いそうなことを伝えてあげると、やる気もアップするし覚えもよくなります。
お手伝いが終わった後は、ちょっと大げさなくらい「ありがとう」を伝えてあげると、子供はより満足して「次もお手伝いしよう」と思ってくれるようになります。
子供にお手伝いをしてもらうときに気をつけたい4つのポイント
最後に、子供にお手伝いしてもらうときの気をつけたいポイントを4つご紹介します。4つのポイントを押さえると、よりお子さんの成長にとってお手伝いが良い経験となりますよ。
子供がお手伝いしたくなるまで待つ
お手伝いはあくまでも、子どもが「やりたい」と思ったタイミングで始めるのがベストです。
お手伝いをなかなかやらない子も、まだそのことに興味が持てないだけだったりします。やる気がないとか、消極的なわけではなく、気持ちが向かないだけなので「強制しない」ことが大事です。
その子が興味のあることで、何かお手伝いできることをお願いしてあげるとやってくれるかもしれません。
遊び要素を入れてあげることも、楽しくなって興味をもってくれるようになるので、おすすめです。
ママ・パパと一緒にやる
親子で同じ動作をすることはとても良いです。子どもとのコミュニケーションとスキンシップを同時に取れるので、ぜひ一緒にやりましょう。
みんなで楽しくやっていると子供もお手伝いが楽しくなって、良い習慣として身につくきっかけにもなります。
また、お手伝いの中では「見る」というのもとても大切です。包丁の使い方や食材の取扱い、火の取り扱いなど、子どもにはまだ出来なくても「見ること」で多くのことを学んで、吸収していきます。
失敗しても怒らない
小さい子のお手伝いでは失敗はつきものです。失敗しても怒らない、罪悪感を与えないことが大切です。
大人にとっては失敗したように見えることも、子どもにとってはできたと思っていることがあります。お手伝いすること、そのことに取組むこと事態が学びになっています。
「これも子どもの経験」と思って好きにやらせてあげる気持ちでいると、子どもはお手伝いが好きになるし、ママ・パパも楽しくできますよ。
焦らせない
子どもを急かしてしまうと余計に上手くできなくなってしまいますし、失敗してしまうきっかけにもなってしまいます。
・休日など時間があるときにお手伝いしてもらう
・時間がなくても簡単にできる事を用意しておく
・おもちゃで代用する、など焦らせないでできる環境を作ってあげて、お子さんも親御さんも気持ちよくできるようにしていきましょう。
お手伝いの練習・代用をおもちゃでしよう
お手伝いで必要になる能力はおもちゃでも練習ができて、育てることができます!
料理では指先の力が必要だったり、細かい作業が必要なことが多いですが、おもちゃで遊ぶことでその力を育んでいくことができます。
例えば、
①型はめパズルやルーピングのおもちゃは「物をつまむ」という動作
②ひも通しやねじ回しなどのおもちゃは「ひねる、通す」という動作
③積み木やブロック、コップ重ねなどは「揃える」という動作
これらの力を育むことができます。おもちゃで遊ぶことを通して、自分の身体の使い方を学んでいくことができます。
他にもおままごとセットやおままごとキッチンなどで遊ぶことで料理の手順を教えられたり、包丁の持ち方やピーラーの持ち方を教えられたりするのでおすすめです。
おもちゃのサブスクもおすすめ!
指先や手を使った遊びができるおもちゃは、日々の遊びを通じて子どもの成長を促してくれます。
ただ、いろんなおもちゃを用意してあげたいけど、全てそろえるのには限界がありますよね。おもちゃのサブスクならひも通しやブロック、積み木などさまざまなおもちゃをレンタルすることができるのでおすすめです。
おもちゃのサブスク「ChaChaCha」では、
- 2ヶ月に1回、発育に合わせてプロがおもちゃを選んでくれる
- 1月あたり3,630円(税別)で6つのおもちゃを遊ばせられる
- 普段選ばないようなおもちゃも届いて楽しい
という特徴があり、多くのママ・パパから好評いただいています。
子供の成長は早く、あっという間におもちゃも買い替えの時期がやってくるものです。そのたびに購入していると大変です。おもちゃのサブスクはお財布にも優しく、またおもちゃを探したり、買いに行く時間が削減されるので、子育てで忙しいママやパパにおもちゃのサブスクはピッタリです!気になるママ・パパは、ぜひ一度「ChaChaCha」のサービスやプランをチェックしてみてくださいね。
お手伝いはお子さんの生活力や自立といった成長を促すとともに、親子の良いコミュニケーションになります。
ぜひ、家族みんなで楽しくやっていきましょう!
chachacha(チャチャチャ)は、
お子様の成長に合わせておもちゃプランニングをし、定期的にお届けする定額制サービスです。
そんな選んで遊べるおもちゃのサブスクが、初月1円でお試しできます!
おすすめ記事

2024/04/01/
コラム【2024年最新版】妊婦プレママ&プレパパ無料特典まとめ!全員もらえるキャンペーン何がある?

2024/02/13/
コラム【生後1ヶ月】赤ちゃんの授乳間隔をわかりやすく解説

2023/09/06/
コラム三歳児の成長・発達の目安は?イヤイヤ期や反抗期の対策も徹底解説

2023/09/29/
コラム4歳児の成長・発達とは?「4歳の壁」の特徴や対処法も解説

2023/10/31/
コラム【2023年最新】1歳向けの知育玩具の人気ランキング20選

2023/09/29/
コラム妊娠中にもらって嬉しかったものは?妊娠中に役立つもの7選!